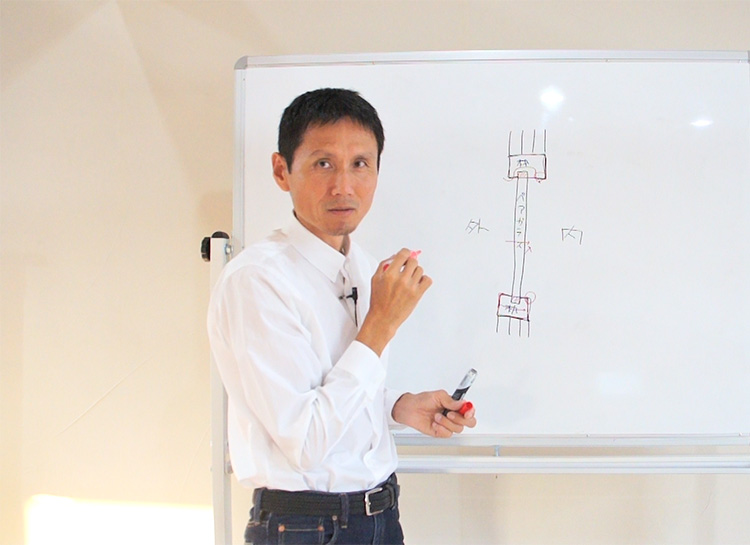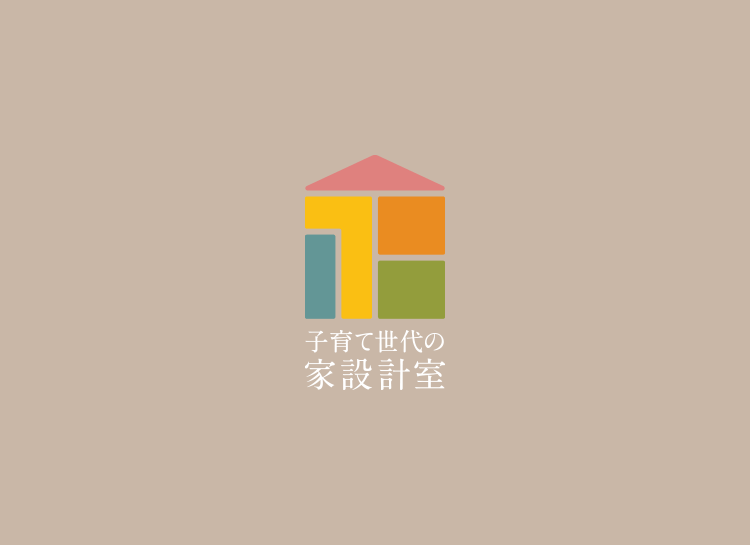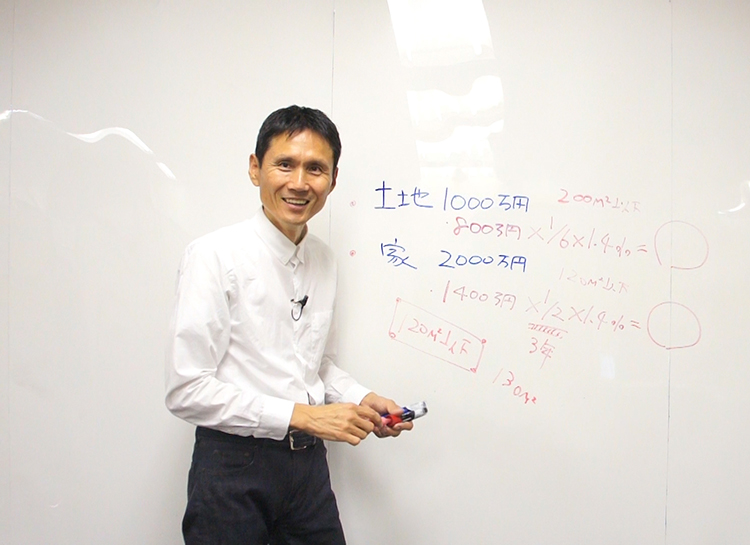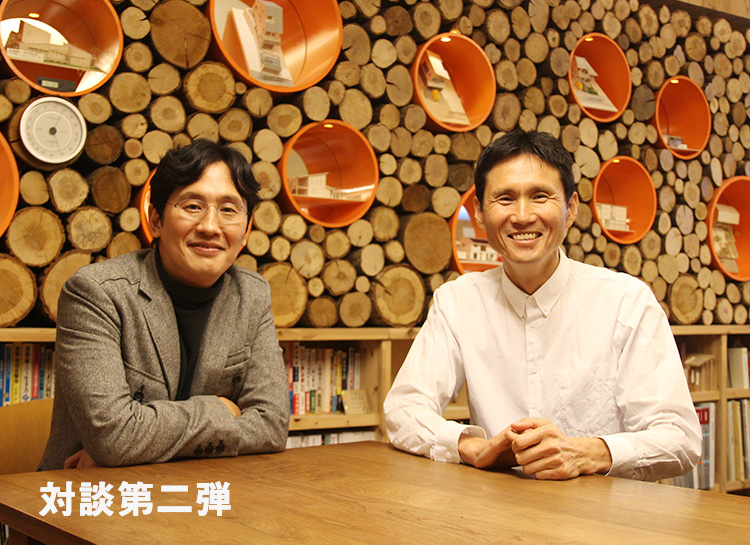今回は、私の配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。
ようやく秋らしくなり、冬に近づいてきました。今朝はちょっと寒いぐらいでした。真夏のすごく暑い時は、夏涼しい家にするために、窓をつけないなどと提唱されている住宅会社さんも見受けられましたが、世の中はそんなに単純ではありません。私のYouTubeやメルマガをお読みいただいている方は理解していると思いますが、やっぱりそうは言っても冬は寒いです。夏は暑くても、今度は気候変動でガクンと寒くなっていくわけです。なので、夏涼しい家だけを作るというのはまずいと思います。
あとは、雪が降るところはとんでもなく降りますが、降らないところでは全く降りません。ただそれも気候の変動によって変わってきているので、一概には言えません。やっぱりそこは、地元の工務店さんがチューニングしていかなければならないと思います。一辺倒に、窓をなくしてUA値を下げることを正義とするのはどうなのかなという感じがしますが、これからはそのような家がどんどんできあがっていくんだろうなと思います。
コストを抑えて補助金も貰えるというのはいいことかもしれませんが、家づくりは補助金を貰って終わりではありません。若い方であれば50年ぐらいはその家に住むわけなので、それぐらいの単位で考えた方がいいんじゃないかと思います。また、性能だけよければいいというのも違う気がします。いろいろな人の考え方があるのでどれが正しいとは言えませんが、よく考えて家づくりをされることをオススメします。
本題に入ります。1つ目のコメントは、空調についてです。
「屋根裏エアコンと床下エアコンのように冷房と暖房を分けるのはいいと思いますが、いかんせん冷房で使うとカビがやばくないですか?最近の気候で夏中つけっぱなしにしているから、シロッコファンが結露しまくって、クリーニングしても1年でまたカビだらけになります。カビを防ぐ方法や、シロッコファンの部分が結露しにくい機種とかってあるんでしょうか?ちなみに6地域G2グレードの三種換気の家です。」
屋根裏エアコンは、基本的に冷房だけで使うものなので、水がどんどん中で回ります。暖房にも使うようであれば、冬に乾燥させることができますが、やっぱりそれだけに使うとなるとまずいです。なのでメンテナンスをしましょうということを、メルマガなどで言いました。
カビを防ぐ方法というのは厳密に言うとありませんが、定期的にエアコンを暖房運転して水分を飛ばすことで、防止することはできます。最近のエアコンは、ストップすると一定時間、中をクリーニングしてくれるものもあります。また、カビをカットするような機能がついているものもあります。ただ、ずっとつけっぱなしの場合そうはならないので、どこかで止めなければなりません。
当社の屋根裏エアコンは、普通のリモコンでも作動しますが、スマホのアプリからでも作動させることができます。壁掛けエアコンがインターネットに繋がっていれば、外部からスマホでオンオフができるようになっているわけです。休日や会社に行っている間など、家の中に誰もいない時間帯に暖房をしてもらって、帰宅する何時間か前に屋外からスマホでスイッチをオンにすれば、家に着く頃には快適になっているという風にすることもできます。1〜2週間に1回やる必要はありますが、そんなに大変じゃないかなという感じはします。
当社のOBさんの中には、毎週末はエアコンをクリーニングすると決めている方もいます。公衆トイレを誰が掃除したか書くような感じで、カレンダーにチェックしていくわけです。たまに忘れてしまったとしても、やらなければ機械が爆発するというわけではないので、問題はありません。そういうことをしていけばカビ防止になりますし、1〜2年に1回エアコンクリーニング屋さんに頼んで思いきり洗浄してもらうよりもいいんじゃないかと思います。
あとは、エアコンに吸気させる空気を一種換気で除湿して、水分をこすり取って、それをエアコンに吸わせることでエアコンの中の水分量を減らすという方法もあります。これは実は、昔からやられていた方法です。理論的にはいいですが、短所もあると感じています。それについてはここでは言いませんので、メルマガなどに書いてあるのを見ていただけたらと思います。物事には必ず長所も短所もあるので、それを見ながらどうするのか考えることが重要です。
私は、機械をなるべく使わない方向でやりたいと思っています。機械は必ず壊れるものなので、壊れてお金がかかるとなると気分が悪いじゃないですか。手間もかかるし、面倒臭いというのもあります。なのでお金がかからない方法とか、あまり手間がかからない方法をとった方が、気分もいいですよね。
ちなみに、北海道はすごく寒いから、一種換気を使うと思う方もいるかもしれませんが、実は三種換気を使うことがほとんどです。意外にも一種換気は、本州の暖かいところで、夏の湿度対策のために使うという風になってきています。なので、関東や本州の平地、標高500m以下みたいなところで、冬対策に一種換気を使うというのは、あくまでも私の考え方としてはないのかなと思います。
西の巨匠のいるところはものすごく湿度が高いですが、一種換気を使うケースもありますし、使わないケースもあるそうです。実際に実践しておられるので、こういう方法もあるんだなと学ばせてもらっています。どっちを選ぶかはお客さんの好みもあるし、コストの問題もあると思うので、こっちじゃないといけないということではありません。当社で家づくりを検討されていて、ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ご相談いただければと思います。
現状の温暖化がこれからどうなるのかは誰にもわかりませんが、ビルゲイツさんは「温暖化はそんなに問題じゃない。」と言い始めたそうです。温暖化について騒いで、お金を注いでいたビルゲイツさんが、最近になって違う発言をしてきたのは、なぜなのか気になりますよね。トランプの圧力もあるのかもしれませんが、もしかしたらいろいろなデータが出てきて、そこまで騒ぐことじゃないということがわかってきたのかもしれません。それで少し修正をし始めたのかなという感じがします。
どんどん温暖化して、地球が滅びちゃうぐらいのことを言っている方と、あくまでも地球の長い周期の中で、こういう時期はあるんだということを言っている方の、2つの勢力があります。国連はどっちかというと、前者の方です。それがさらに今はビジネス化してきちゃっています。
EVというものも出てきましたが、製造や充電の問題により、結局はトヨタさんが昔から言っているハイブリッドの方がいいんじゃないかという話になりました。EVに散々投資したドイツの自動車業界は、かなりメタメタになってきてしまっています。こういうことも事実としてあるので、よく考えた方がいいと思います。
私は経済学者でも陰謀論者でもないですが、いろいろな情報を普段から取っておかないと、世の中に惑わされちゃう感じがしています。正に「選んでいるようで、実は選ばされている。」という状態になっていってしまいます。なので私のYouTubeでは、家づくりのことだけでなく、そういう情報も出せたら面白いんじゃないかなと思っています。
2つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。
◼︎付加断熱は通気層がいらないのか?
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/fuka_dannetsu_tsuuki/
「北米方式のみ勉強しています。通気層の役割を正しく説明しています。昔直張りだった頃のお風呂のある場所の外壁の色が変わっていますね。湿気が逃げるところがなくサイディングに染み込んでいるんですね。やっと日本も防湿シートの考え方や、棟換気が取り入れられるようになりました。」
北米方式というのは、アメリカ型のパッシブのことです。パッシブにはアメリカ型とドイツ型があるらしいんですが、私は厳密にその違いがわかるわけじゃないので、何とも言えません。ただ、日本で語られるパッシブというのは、ドイツ型の方が多いんじゃないかと思います。現に日本に、パッシブハウス・ジャパンという組織がありますが、そこではドイツの認証か何かを元にしているはずなので、北米方式というのはそんなにまだ普及していないんじゃないかと思います。
日本の気候とパッシブが合うのかどうかということについては、思うところがあります。やっぱり日本には日本の気候があるので、日本独自にチューニングするべきじゃないかという感じがします。日本はヨーロッパと違って単一な気候ではなく、沖縄から北海道までいろいろな地域性があります。さらにその中でも、海に近くてすごく湿気があるところもあれば、群馬みたいにガーンと41.8℃ぐらいになるところもあるわけです。
当社の施工エリアでいうと、足利市や桐生市は、山の向こう側の日が当たらないところと当たるところで全く温度感が違います。そうなると、窓のつけ方から断熱方法まで変えていく必要が出てきます。予算的な部分で変えられない場合は、空調で補ったり、間取りを変えたりする必要があります。そういうのをチューニングと言うと思いますし、やっぱり地元工務店にしかできないことだと思います。間違いなく大手ハウスメーカーさんにはできません。大量に売れないので、やる気もないはずです。
なので、地元工務店さんがなるべく簡単に売れるようにと、規格の住宅ばかり作るとか、スマホで発注OKみたいなシステムを取り入れるというのは、ちょっと違うんじゃないかという感じがします。ただ、そういうのが素晴らしいと称賛するような住宅雑誌もあるのは事実です。間取りを限定して販売することで効率的な経営になるし、なおかつ社員にも職人さんにも負担がかからず、打ち合わせも数回で済むといった内容でした。
住宅会社さんから見れば、手間をかけずに売れて、発注も楽で、コストも削減できて、利益幅が増えるのでいいかもしれませんが、住まわれる方からしたら「それは本当にいいことなのかな?」と思いますよね。家は同じ場所に建てていくわけではなく、いろいろなところで建てるものです。それなのにそういう家をひたすら作り続けるのは、どうかと思います。
たしかに、建築コストがアップしているような今の時代にはありかもしれません。ただ、住まわれる方の目線で見たら、いいことだとはあまり思いません。私が古い人間なのかもしれないし、経営者目線からズレているのかもしれませんが、最近はそういうことが本当に増えてきた気がします。雑誌でもそういうのが素晴らしいと言われているということには、違和感があります。話がまたいつもの通りどこかに行っていますが、こんな感じで終わります。