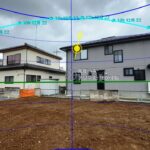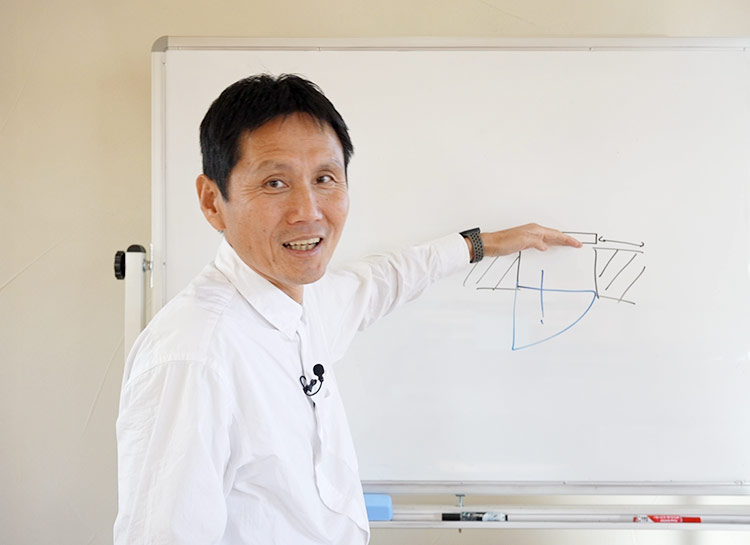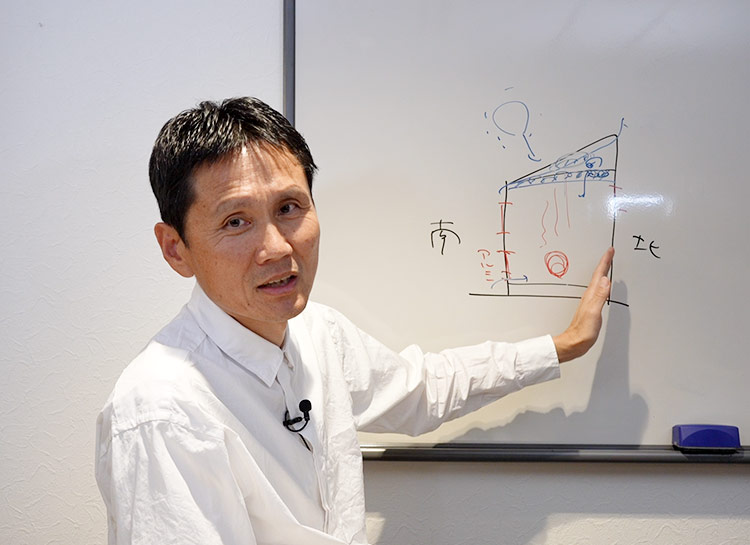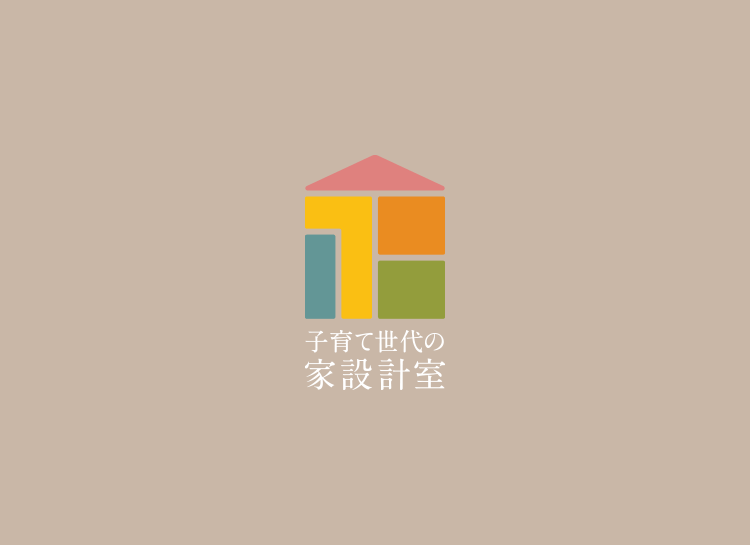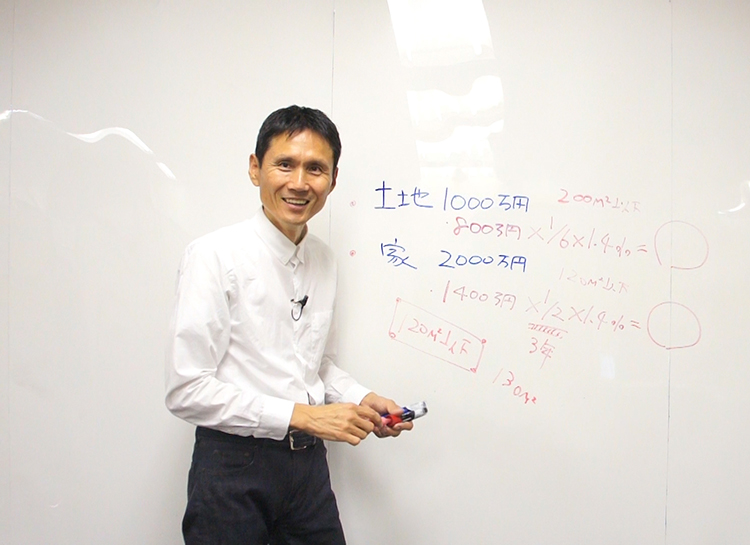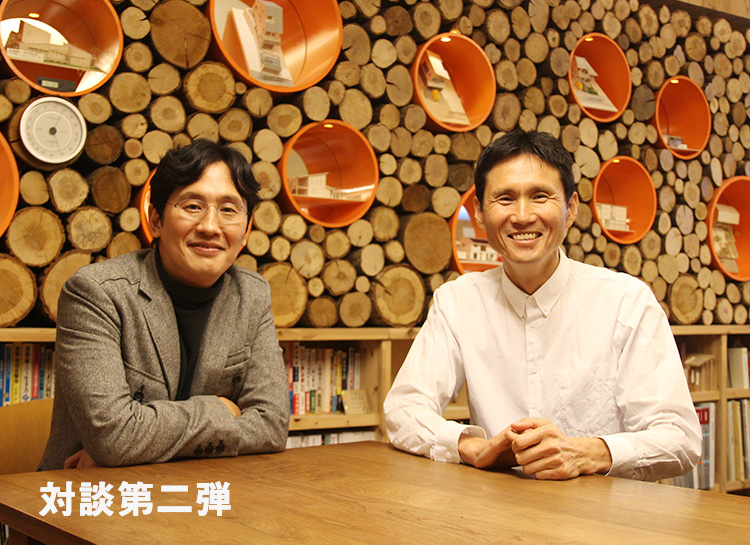今回は、私が配信させていただいたメルマガに対する感想をご紹介します。
早速ですが、1つ目の感想です。
「小暮社長様、面白い題材のご提供をありがとうございます。“選ばされている”のに気づかない方は大勢おられると思います。選択は自由ですけど。
話は変わりますが、1日で建ってしまう家を目撃しました(驚きです)。小暮社長なら当然ご存じでしょうけど、小生は目の当たりにしたのは人生の中で初体験でした。ト〇タホームと〇水ハイムの現場が近くでほぼ同時期にあり、何気に観察しておりましたが、ある日トレーラーに箱型の部屋、ユニット(何というのかわかりません)が運ばれてきてクレーンで積み上げていました。
あまりに機械的な出来事でしたので、呆気にとられてしばしその工事を遠目に見ておりました。選ぶのも選ばれるのも個人の選択ですが、あれは“家”なのかなぁ?と、疑問というか不思議な感覚に陥ったものです。」
ユニット工法の家が最適だというシチュエーションもあると思います。例えば、狭い場所で足場を建てて作業する際には、ものすごくいいんじゃないかと思います。また、斜線制限がある場合でも、効率がいいと思います。ただ、当然マイナス面もあります。
まず、工場の規格に合わせて作られているので、自由設計はほぼできないという点です。以前、ご実家がユニット工法の家という人がモデルハウスの見学に来てくれたんですが、子どもの頃は2階が暑くて困ったと言っていました。鉄フレームなので、熱橋がすごいわけです。熱損失も大きいし、窓もアルミじゃないと持たないんじゃないかと思います。結露もすごいと聞いたことがあるので、いいところも悪いところもある感じがします。
また、工場で作るので効率的ではありますが、結局は工場を動かすための経費が高くなるので、その部分もデメリットかなと思います。狭いところに高層で建てるとか、斜線制限があるという場合はいいですが、田舎の畑の中で建てるメリットはそんなにないかなという感じがします。でも、意外にそういう場所にポンと建っていることもあるので、不思議だなと思います。
2つ目のコメントです。
「小暮社長様、様々な問題点を投稿されておられることにプロ意識を感じ取れます。取捨選択ができないように誘導しているYouTubeとか、本当に理解できないご時世になってきましたね。
ふと疑問に思い、業界プロの小暮社長にお聞きしたいことがあります。よく世間では有名建築家がマスメディアなどに登場されていますけど、彼らはデザイナーではないのでしょうか?その方々の作られた物件に問題点が指摘されているようですが、その方々は今回小暮社長が述べられている経験値がどこまであるのかと、単純に違和感を覚えます。なぜ建築家という呼称があるのに建設家というジャンルがないのでしょうか?違和感という感性は大事だと、いまさらながら思います。」
おそらく、隈研吾さんのことを言っているのだと思います。隈さんが作った木の家にカビが発生していると、一時話題になったことがありました。群馬県でも、隈さんに頼んでカビが生えたという人がいたので、実際に見に行ったことがありますが、見た瞬間に「これはカビが生えるだろうな。」と思うような状態でした。
隈さんは忙しい人なので、あくまでも隈さんの部下の方が設計して、隈研吾印を押して作っているのかなと思います。さらに、わかっていない者同士でやっているから、ああいうことが起こるんだろうなという感じがします。本来であれば、施工する工務店さんが監修するはずですが、隈さんの設計したものに対して「これは腐りますよ!」なんて言えないじゃないですか。なので、そのまま作るしかないんでしょうね。
隈さんも設計事務所も悪いとは思いますが、もう一方で、「その市町村の建設課は何をやっているの?」という風に思いました。きっとそこの方々は、図面を見ても何もわからないんでしょうね。「隈さんが作っているからいいんだ!」と言って税金を使っているんだとしたら、かなり問題だと思います。
「話は変わります。グラスウールという断熱材がありますが、小職に多少関係がありました。ガラス溶剤を細かいフィルターのような穴を通過させて糸くずを作り出すのですが、このフィルターのような部材の製造にも関与しておりました。当時の穴あけサンプルを常に持ち歩いて、ハウスメーカーや工務店の方々にグラスウールの製造方法を解説しましたが、100%誰もご存じではありませんでした。少なくとも自分たちが使用する部材については興味を持ってほしいとも思ったのも事実です。
ハウスメーカーも工務店の方々も売ることが目的になっていると、小暮社長のご指摘通りです。掘り下げて自分たちの仕事の中身を大切にしないと、人には伝わらないのでは?と、今回のメルマガを拝読して思った次第です。」
グラスウールの製造については、前にメルマガで解説しました。ガラスを溶かして、遠心分離機で回して、ピューピューと出てきた糸みたいなものを編んで作ります。なるべく細くいっぱい編めば、高性能なものができます。それをご存知の方は誰もいなかったとのことですが、たしかにいないと思います。
今、住宅業界にいる方で、家づくりが本当に好きな方というのは少ないんじゃないかと思います。仕事としてやってはいても、そんなに好きではない気がします。本当に好きであれば、グラスウールはどうやって作るのかとか、発泡ウレタンのこういうところがいいんだということを調べるはずです。現場にいたいとか、測定したいとか、研究したいという欲も出てくると思います。
なので、日々の業務はやっても、それ以外は特にやらないという人がほとんどじゃないかと思います。また、それ以上の知識をつけようと思うような人は、今は本当に少ないのかなという気がします。大手ハウスメーカーさんは本当にそうだと思いますし、地元工務店の方でも、そういう人は少ないと思います。
先日、お客さんと打ち合わせをした時にもそういう話になりました。家はただの物体じゃないですか。材料を買ってきて、職人さんに組み立ててもらうものです。なので、その物体の中に感情があるわけではありません。木やコンクリート、鉄筋やグラスウールといった物体を、同じように組み立てる作業をするだけであって、そのもの自体に感情はないのが普通かもしれません。ただ、作る側の人間に感情がなければ、いいものはできないんじゃないかと思います。感情があるのとないのとでは、最終的な結果は違ってくる気がします。
今は売ることが目的になっていて、流れ作業のようになってしまっている感じがします。車みたいに雨風をしのぐような空間の中で、ビスを止めたりはめたりするのは、別に感情がなくてもできると思いますが、家は車のように単純化しているものではありません。なので、そういう部分に対して感情が付属していなければ、家づくりというのはなかなか上手くいかないんじゃないかと思います。
3つ目のコメントです。
「小暮様、初めて感想を書かせていただきます。いつも楽しく拝見しています。元々は松尾先生のYouTubeから小暮先生のことを知り、嘘偽りのない話をされているのが非常に見ていて楽しいです。数年前に家づくりをし、その時の打ち合わせ等が非常に楽しかった反面、自分の家がどの程度のものかを知るために、いろいろ調べてしまいました。知れば知るほど、自分がいかに勉強不足だったかを痛感しました。後悔する部分もありますが、できる修正を行い、子どもと楽しく過ごしています。次は松尾先生に設計をお願いすることを夢見ています。
この度感想を書きましたのは、“家は最初に間違った選択をしてしまうと、なかなか取り返しがつきません。”という言葉です。胸に突き刺さりました。自分は医療者で、市民向けに講演もしていますが、小暮先生の言葉通りです。医療の世界もエビデンスというものを構築しているはずなのに、変な解釈をする人や、眉唾なことを言う人が多いのが現実です。小暮先生のよく言われる“違和感”がキーなのかもしれません。」
たしかに、医療の世界でもそういう話を聞いたことがあります。1つの部門の医療の中で実際に行われていることというのは、はっきり言って医者自身もよくわかっていないそうです。でも、日本の医療では、それを追求しようということにはならないそうです。
アメリカだと、さらにその専門家がいるようですが、日本だと「薬はこれです。」と言って終わりです。“変な解釈をする人や、眉唾なことを言う人が多いのが現実です。”というのは、本当にその通りだと思います。
住宅業界にも、変な人はいます。「その工法はまずいんじゃないか?」と思うようなことを、いかにもいいことのように言っている人を見たこともあります。なので“違和感”という、人間が本来持っている機能を使わないとまずいわけです。でも今はその違和感を、自分で勝手に「ホームページには書いてあるんだよな。」「このYouTubeは登録者数が多いんだよな。」と、消してしまう人が非常に多くなっている感じがします。
“最初に間違った選択をしてしまうと、なかなか取り返しがつきません。”というのも、おっしゃる通りです。何度も他の動画で言っていますが、今は施工というのが1つのキーワードかなと本当に思っています。UA値、C値、樹脂窓、付加断熱、セルロースファイバー、発泡ウレタン、グラスウール、通気といったものも当然大事です。ただ、それをどういう風にちゃんと組み立てるかという、施工の部分についてちゃんとチェックしていかなければいけなくなっていると感じます。
今は、現場監督も職人も人手不足だし、素人化が進んでいます。職種によっては、高年齢化してしまっているものもあると思います。決して高年齢化していることを馬鹿にするわけではありませんが、昔と今とでは施工が違っている場合もあるので、こういうところも含めて、視聴者の方には気をつけていただきたいと思います。