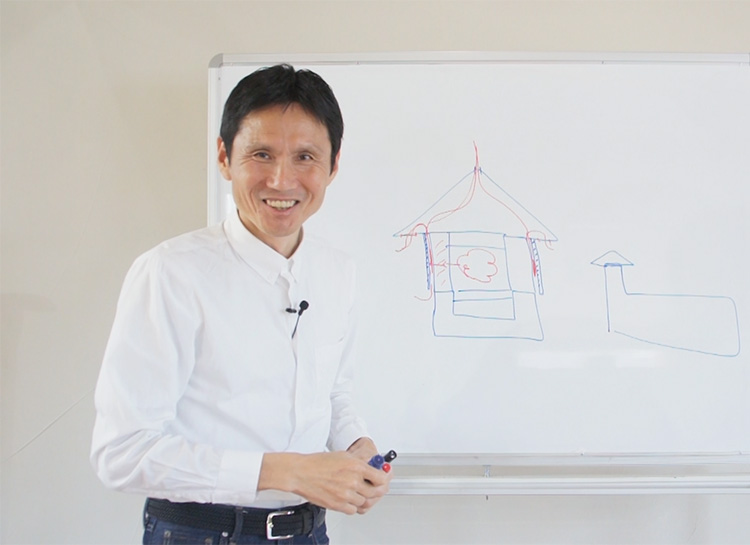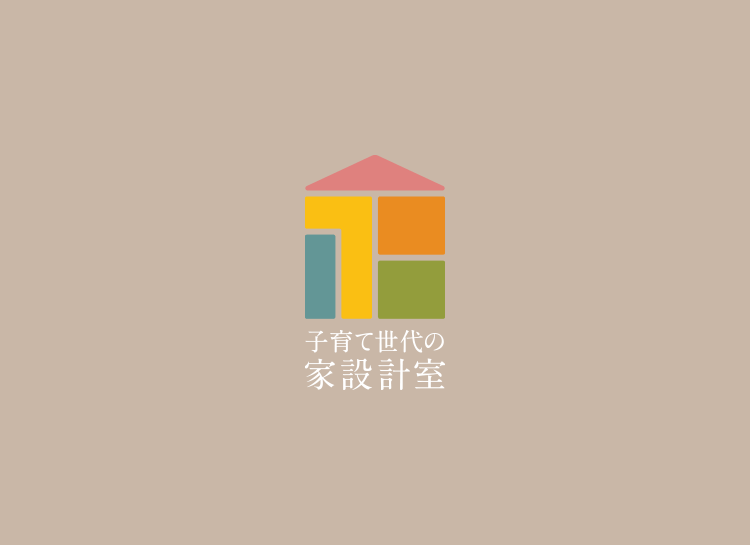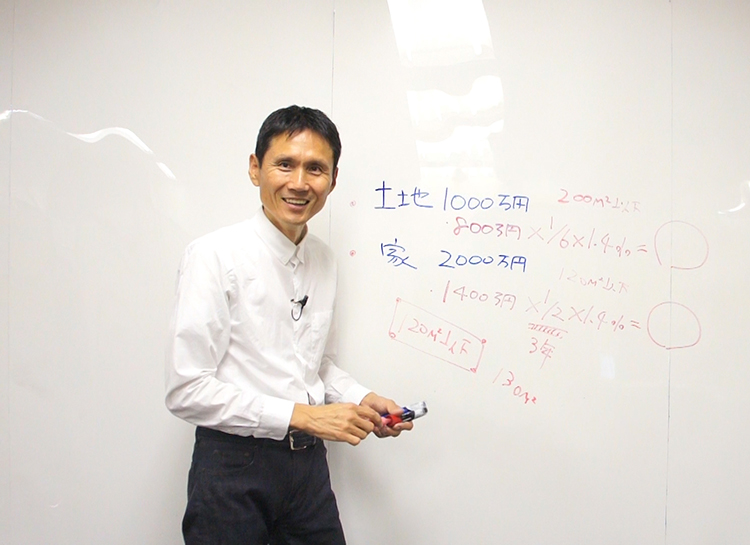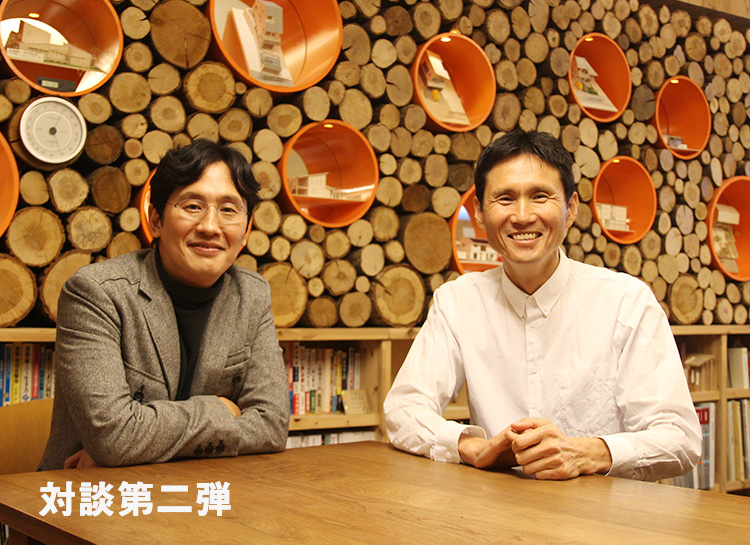今回は、除湿の方法やエアコンへの負担について、お話ししたいと思います。
日本の気候は亜熱帯化しているという風に、みなさんも感じているんじゃないでしょうか。近頃は湿度が高く、ジトッとした日が続いているので、エアコンに対しても負担がかかっているようです。そのため、エアコンが壊れやすくなっているような気もします。
亜熱帯型エアコンなんてものはありませんが、高温に強いエアコンは出てきています。外気温50℃対応のエアコンも出てきていますが、外気温が50℃になることはなかなかないと思うので、それよりも湿度対応エアコンを作ってもらいたいところです。
屋根裏エアコンの室外機は、基本的には日が当たりにくい方に持って行くのが原則です。西側でもいいですが、日が当たらないような状況にした方が室外機の回転はよくなります。床下エアコンに関しては、暖かい方に持って行くのが理想です。ただ、わざわざ暖かい方に室外機を持って行っても、配管が伸びて効率が悪くなっては困るので、なるべく配管距離を短くした方がいいかと思います。
夏にエアコンを壊さないためにも、5月ぐらいの少し暑くなってきた頃に試運転をしてもらって、ちゃんと動くかどうかということをテストしてもらいたいです。そこでちょっとでもおかしいなと思ったら、早めにメーカーさんにメンテナンスを頼んでください。お客さんによっては、暑くなってからおかしいということに気づくので、ここは本当に守っていただければと思います。
今はエアコンに対する負担が大きいので、エアコンのメンテナンスというのはものすごく重要です。フィルター掃除もたしかに大事ですが、エアコンの中に入った水分を乾かして排出させることは、それ以上に大事です。ドレンポンプというものを使ってやっていただくわけですが、2階に室外機がある場合、梯子がなければできません。そういう場合は、エアコンを暖房運転させることで乾燥させるということをしてもらいたいです。
マメに暖房運転をして乾かしてもらうのが一番いいですが、夏に毎日暖房をつけるわけにはいかないので、どのくらいの頻度でしなければいけないということはありません。ただ、最低でも月に1回ぐらいはしてもらうといいかと思います。それに加えて、エアコンを使い終わったら必ずドレンポンプで水を抜くとか、フィルターを掃除するということをオススメします。
方法については、お客さんに動画で解説したり、文書で渡したりしていますが、当然やる方もいればやらない方もいます。決して強制ではありませんが、しっかりやっている方のエアコンは壊れていない感じがします。エアコン洗浄もいいですが、今言ったような自分でできるメンテナンスをした方が、手間はかかってもお金はかかりません。また、1年に1回バーンとやるよりも、マメにやった方が機械にとってもいいんじゃないかと思います。
屋根裏エアコンは、暖房で使う人もいるでしょうけど、基本は冷房で使っている人がほとんどだと思います。そうなると、乾燥する機会がなかなかありません。逆に床下エアコンは、暖房でしか使わないので本当に壊れません。やっぱり機械というのは水に弱いんだなと思います。
今のエアコンは安いし、昔に比べたら耐久性が落ちていると思います。なので、たった12万円くらいの機械に負担をかけるのは、なかなか厳しいんじゃないかと思います。昔のエアコンは今のものよりも大きく、省燃費ではありませんでしたが、その分、耐久性はあった気がします。また、そもそも昔は今のような湿気はありませんでした。いずれにしても、今は機械のメンテナンスが間違いなく必要な時代になっているので、参考になればと思います。
亜熱帯化して湿度が高くなっている中で、除湿をするというのは1つのポイントだと思います。他の動画でもお話ししたと思いますが、除湿する方法は大きく分けて3つあります。エアコン使うという方法、除湿器を使うという方法、日射取得をするという方法です。中でも除湿器を使うという方法は、なかなか難しいです。コンパクトで気密性が高い家であれば簡単ですが、大きな家で除湿器を使って除湿をするとなると、上手くいかないし、エネルギーコストもかかります。当社のお客さんでもやっている方はいますが、エアコンを使った方が早いかなという感じがします。
それよりももっと簡単で、私がいつもお客さんに提唱しているのは、ある程度日射を入れてもらって、水分を飛ばしながらエアコンを動かして、より除湿をしていくという方法です。以前に私のFacebookやXで、事務所で仕事をしている時の温度計を見せたと思います。室温が29℃、湿度が30%だったので、ちょっと乾燥している感じもしますが、絶対湿度的には最高の状態です。ただ、そのくらいの温度と湿度にするのは、いくら高性能住宅を作ったとしても難しいです。
じゃあなぜ事務所ではそんな状態になっているのかというと、鉄骨で、アルミのシングルガラスで、日射取得量がものすごいからです。室内が思いきり乾燥するので、エアコンをちょっとかけてあげただけで冷えますが、エアコンを止めた瞬間に暑くなります。ちょっと極端な例ですが、そういう方法も無きにしも非ずということです。
窓ガラスもハニカムブラインドも全部開けて、ガンガン日射を入れて、エアコンをかけたらどうなるのかやってみると、新しいヒントが出てくるかもしれません。極端なことをやるとこうなるんだとか、ここまで開けると流石に無理だなとか、新しい発見があるかもしれません。
去年の5月にお引き渡しをした前橋のお客さんは、すごく上手に調整されています。「どんな感じで使われていますか?」と聞いたところ、以下のようなメールをいただきました。
「お家の状況ですが、6月に入ったあたりから、天気とタイミングによって、ハニカムブラインドとアウターシェードを使い分けながら過ごしています。エアコンの温度は25〜26℃に設定しており、室温はおおよそ26〜27℃前半という感じです。湿度も40%台で、体感的にもとても過ごしやすいです。今年は毎日妻と赤ちゃんが家で過ごしているため、日中も室温と湿度をコントロールしやすいのは昨年以上にありがたく感じます。」
室温27℃、湿度50%くらいというのは、ずっと家の中にいても暑くも寒くもない状態だと思います。代謝がいい人だったらもっと下げたいと思うはずなので、全員にとっていいというわけではありませんが、お客さんから話を聞いていると、室温は27℃ぐらいがちょうどいいという人がほとんどです。
湿度50%というのは理想であって、実際には55%以下ぐらいだと思います。これは屋根裏エアコンの使い方に気をつけることと、日射を少し入れるということで実現できます。この辺りは言葉にするのは難しいので、やってみてこういう感じなんだと覚えるしかありません。
ちなみに、夏場に日射を入れることで室内の湿度をコントロールするというのは、誰かに教えてもらったわけではありません。もう何年も前に建てたお家の湿度がなかなか下がらなかったので、窓を開けて放っておいたところ、グングン下がっていったことから、夏も日射を入れなければダメなんだとわかったわけです。
当社の事務員さんのお家は、某◯条工務店さんで建てられたんですが、やっぱりそのお家も閉じている感じがします。営業さん自身も「ハニカムブラインドは全部閉じてください。」と言うそうなので、その通りにしたところ、家の中の湿度が全く下がらないみたいです。なので「ハニカムを開けて、日射を入れたら変わると思うよ。」とアドバイスをしました。冬はよくても、夏にはマイナスになることもあるので、夏場の湿度対策で気になることがあったら、ちょっと変わったことをやってみるのもいいんじゃないかと思います。
西の巨匠に「夏に日射取得をしてエアコンを動かして、より水分を飛ばすということをやっているんですけど、それはおかしいですかね?」と聞いたところ、意外にも褒められました。高性能住宅を作っている住宅会社の方でも、「何でそんなことをするの?」と言う人は多いみたいです。中には湿度が飛ばないからと言って、ハニカムを締め切ってエアコンの温度をどんどん下げたところ、寒くなって厚着するような人もいるそうです。
頭の中のイメージと現実は違うということは、本当にあります。これも体験しないとわかりませんが、西の巨匠曰く、セルロースファイバーの内側に気密シートはいらないそうです。ただ、セルロースファイバー側に湿気が行った際には、こちら側に抜けるようにするという風に、方向はちゃんとしておかなければいけないみたいです。
私は基本的には安全面を重視していますが、仮にという考え方もあるので、一応通気も取ります。ただ、外壁の温度が上がっていかないと上昇気流は発生しません。この辺りのことは本に書いてあるわけでもないので、事例ごとに学んでいくしかありません。そういう意味では、マニアックなことをやっていくのも必要だと思います。