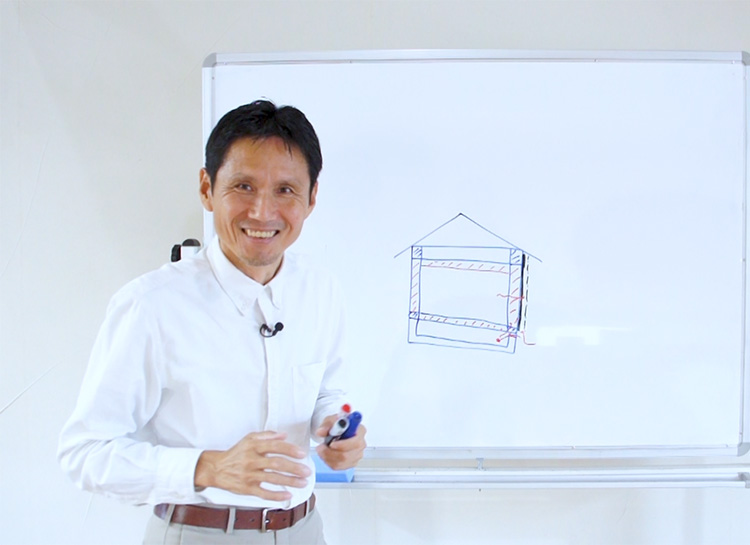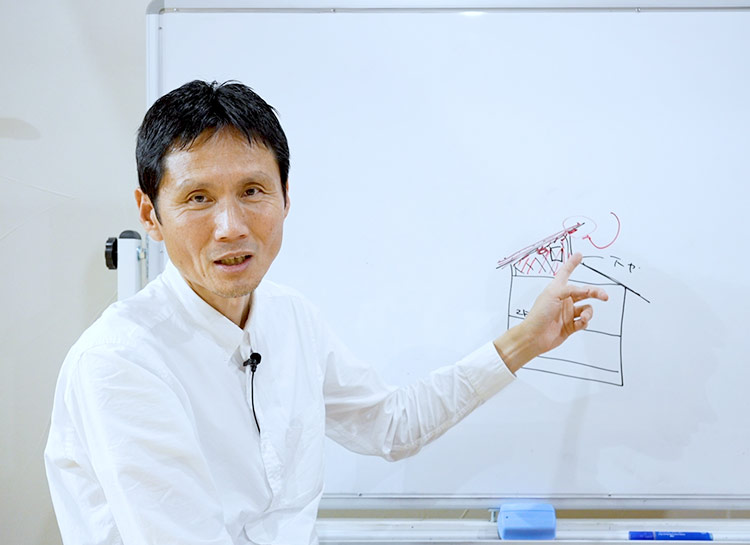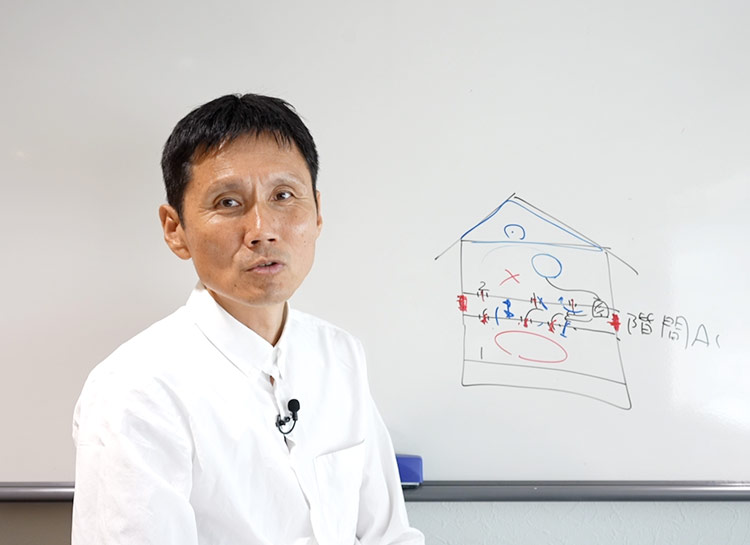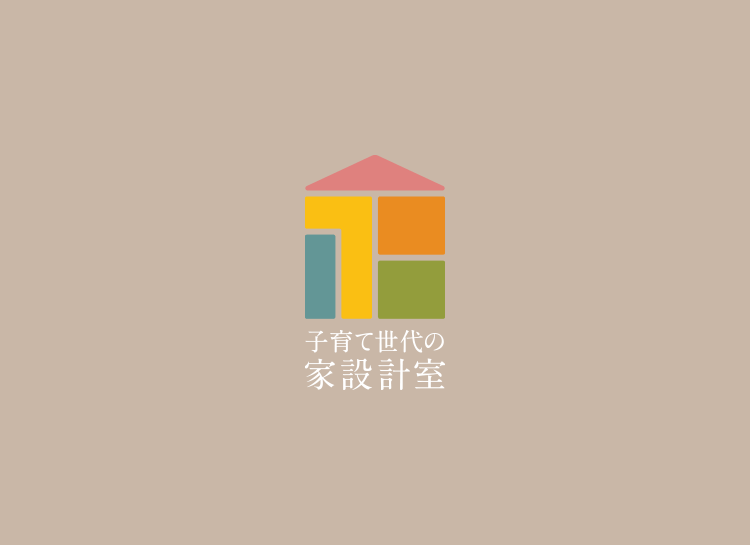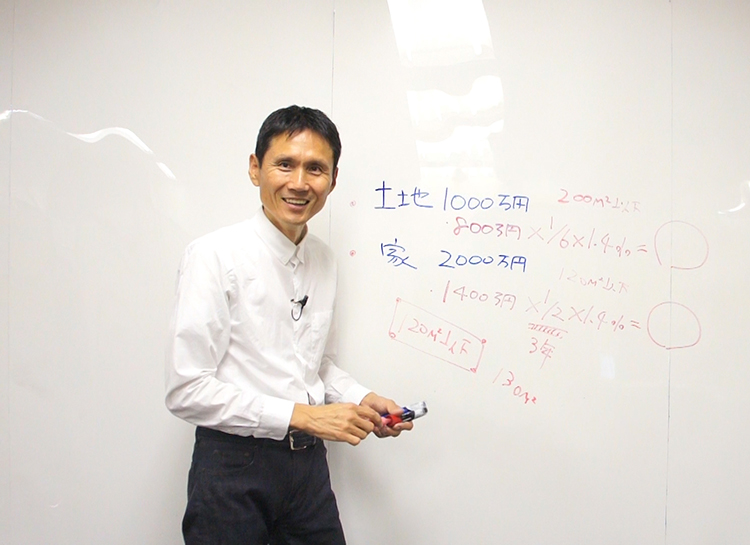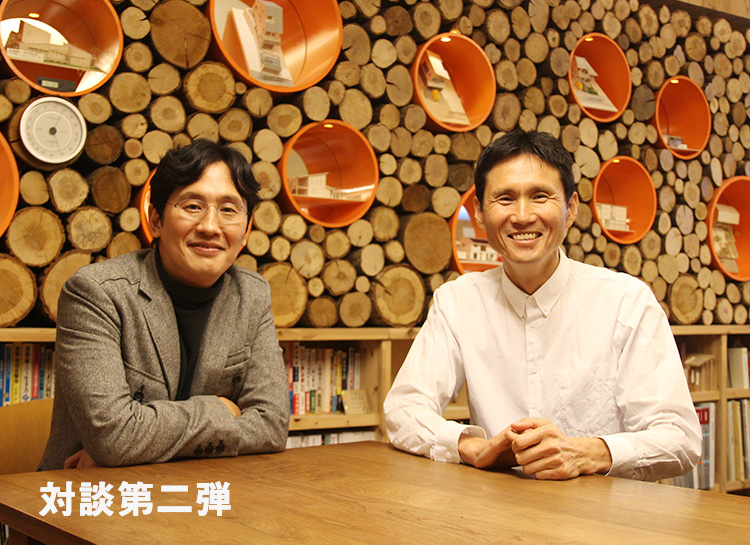今回は、私が配信させていただいたメルマガに対する感想をご紹介します。
1つ目の感想です。nobandさんからいただきました。
「お世話になります。家を建てることって自己満足だと思ってます。だから色んな正義があるのだと。ただ、自己満足って満たされた後って無であったり、別の視点、見てなかった視点において不満足なところが出てきたりしますね。個人的には自分の視界に元々ない提案をできる工務店を選ぶことが長期的な満足度を高めるポイントだと思います。その点において、家の性能といった提案力と乖離したポイントって、案外満足度に繋がりにくいと家を建ててみて感じます。寒くないなー、暑くないなーで終わりですからね。」
おっしゃっていることは本当によくわかります。住み心地、耐震性、UA値というのは家づくりの基本です。ただ、そこだけで満足されてしまうのは、ものすごくもったいないと思います。また、そこに特化しすぎているような家も、満足度が低く、飽きてしまう感じがします。間取りや外構、色使いや匂い、家の中の明るさや光の入り方といった、自分の視界にない提案も大切なんじゃないかと思います。
先日、今年の冬に引き渡しをさせていただいたお客さんのお家に取材に行きました。過去には群馬県渋川市に平屋を建てたお客さんに取材をして、インタビュー動画を作成したことがありますが、おかげさまでその動画は大変好評でした。それをきっかけに家を建てさせていただいたお客さんもいますし、「ああいうシチュエーションはいいよね。」とか「ああいう平屋が作りたい。」という話をいただいたこともありました。
最近、都心にお住まいの方が、群馬や埼玉、栃木の方に移住をしたいというご相談をいただくことが多いです。そういう中で、先ほどお話ししたお客さんは、若いご夫婦なんですが、群馬に移住したいということで、すごくいいなと思い取材をさせていただくことになったわけです。
そのお客さんも、自分の視界にない提案ということについておっしゃっていました。やっぱり素人だから、自分たちがわかることには限りがあるので、いろいろ会話をして「もっとこうやったらいいんじゃないか。」とか「それはいらないんじゃないか。」と言ってもらうことで、視界が広がり、自分たちが行く方向性がより深まったということを言われていました。我々は、そういうところを目指していくべきなんじゃないのかなという感じがしました。
私は30年以上建築業界にいるので、これまでにいろいろな建物を建てさせてもらってきましたが、そういう家はやっぱり飽きないわけです。決まった間取りの家をそのまま買うことは、別に否定しません。ただ、もったいないし、ワクワク感はないんじゃないかなという感じがします。そういうのをどうしても買わざるを得ないこともありますが、選択肢があるのであれば、ワクワク感があるような家づくりを選択することをオススメしたいです。
埼玉県の都心に近いところだと、家も土地も高いじゃないですか。そういうところで、ワクワク感があって自由設計ができる家を建てるのは不可能だと思います。今回取材したお客さんも、全く同じことを言っていました。お2人とも都心の会社に勤めているんですが、周りでは埼玉県の駅近で建売住宅を買ったりだとか、東京でマンションを買ったりした人が多いから、最初はそれも考えたみたいです。別に間違っているわけじゃないし、普通のことだと思います。
ただ、コロナなどをきっかけにいろいろなことを考えた結果、移住をすることで自分たちの住まい方や生き方が変わる気がしたそうです。そこで、当社がお手伝いをさせてもらうことになったわけです。そういうことがなかったら、限られたスペースの中で生活する人生だったと言っていました。決して建売住宅が悪いと言いたいわけではなく、選択肢があるのにわざわざ建売住宅を買うのもどうなのかなという意味で、この話をさせていただきました。
2つ目の感想です。以前YouTubeで取り上げた千葉の方です。
「毎回、本当にありがとうございます。よくぞ、これだけのネタがあるもんだと感心するばかりです。家は奥が深いですね。全国展開のHMやネットワーク工務店などに聞かせてやりたい内容です。今回も共感というより、人生はこういう姿勢で歩みたいものだと思いました。
YouTubeでの“①良いものはよいダメなものはだめ②信頼を得るためではない③当たり前のことを当たり前にやる”特に③は阪神タイガースの岡田前監督の指導とも共通項がありその似通った精神こそがプロとして賞賛される所以だと思います。シンプルな表現ですが、簡単なことではありませんよね。裏付けされた経験と実績、そこから蓄積された知恵を臨機応変に駆使できる能力が言葉から伝わってきました。人の欲望は限りないのでやっぱり落としどころ、分相応がよろしいかと。」
なぜ私にはネタがあるのかというと、現場に出ているからだと思います。発注をしたり、図面を書いたり、職人さんやお客さんと話をしたりと、いろいろなことをやっているからだという感じがします。これが例えば、経営しかやらないとか、お金の勘定しかしないということになってくると、出てくるネタは本に書いてある内容だとか、セミナーで話した内容になってくるんじゃないかと思います。
たまに私の話に出てくる西の巨匠さんは、70歳を過ぎていても、いろいろなところに自分で足を運ぶし、いろいろな会社に見学に行くような方です。新住協に行っていろいろな情報を仕入れたりもするので、話していてもネタがつきません。半分隠居しちゃうと、現場に行かないわけなので、自然と入ってくる情報も少なくなります。そうなると話す内容も、本に書いてあることだとか、誰かが言っていることになる感じがします。情報に対する新鮮味も、なくなっていっちゃうんじゃないかと思います。
当たり前のことを当たり前にやるのは、すごくシンプルで簡単そうに見えますが、実際は簡単ではありません。人間というのは飽きるし、楽をしたいと思う生き物です。なので、魔法を求めるのかなという感じがします。
セミナーにいっぱい行く人がいますが、私の拙い経験からすると、セミナーにたくさん行っている人ほど大体ダメかなという感覚があります。「そんな暇があったら実践しなさい!」という風に思ってしまうわけです。1回でちゃんと覚えてきて、実践して、新しい発見をして、疑問を見つけて解決するということをしなければ、能力は高まらない感じがします。
ただ世の中では、セミナーに何回も行っていると「この人はすごい!」と思われがちです。これは全く逆ですよね。また、セミナーの一番前に座っている人も大体ダメです。そういう奴ほど、書くことが優先になっていて、内容が頭の中に入っていません。すごく熱心に見えるかもしれませんが、実際はそうではありません。本当に熱心な奴は、書かずに話を聞いています。
私もセミナーには出ますが、住宅セミナーよりも、世の中の流れだとか、自分自身のことを考えるセミナーに出ています。でも、若い時はいろいろな知識を吸収していいと思います。そして、ある程度年を取ったら、ちょっと違う方向に行った方がいいんじゃないかと思っています。
上を目指すのもいいですが、上を目指すことだけが正義ではありません。住宅業界の売上、集客、着工数といったものは、ものすごくわかりやすいです。それを目指すのも1つの手ですが、目指せば目指すほどズレてくるというパターンも本当に多いです。この辺りはその人の人徳やレベルによると思います。私自身はどう考えても、数を増やすということはできない、許容量が少ない人間です。人をいっぱい使って、支店をバンバン出して、棟数をボンボン上げて、「社長!」という感じでやるよりは、自分の好きなことを仲のいい職人さんとチクチクとやっている方が楽しく感じます。
前職の時は違いましたけど、そういう方が合っているなと思って、自分で会社を作ったという経緯があるので、今の方が間違いなく楽しいです。でもこれは、お客さんのおかげでもあります。そういうのをいいという風に感じてくれているお客さんが集まってきてくれて、わけのわからない説明を「なるほど!いいですね!」と受け入れてくれて、一緒になって作ってくれて、実際に住んでからも満足してくれていそうな感じがするので、嬉しく思います。
3つ目のコメントです。先ほどと同じ千葉の方です。
「今回はお施主様と小暮社長様のリアルなやり取りが手に取る様に実感できる臨場感満載の投稿でした、自分の時の様にスリリングでもありました。お施主様が小暮社長様に出会われるまでには紆余曲折があったと想像できますが、その結果は本当に羨ましく“良い出会いでしたね”と申し上げるほかありません。小暮社長様の一軒の家に対する想いが伝わってくるプロの貴重な投稿と思いました。
蛇足。小生の場合、遠方(現自宅から160km)でしたが対面は8,9回その他Zoomも数回ありました。小暮社長様ほどのキャリアがある設計士さんではなかったので、彼は都度都度ご自身で確認作業(松尾先生のグループで知り合いの方へ)を行っていたのは技術者といえども、分からない事或いは自信を持って当方に提案するためには必要な作業だったのではと技術営業者の小生は理解できる姿勢でした。」
以前に配信したメルマガに書いたと思いますが、遠くの工務店さんに依頼した家づくりで「うーん?」と思うことがありました。施主さんが遠くの県の住宅会社さんに依頼をしたそうなんですが、現場目線で見ちゃうと、現場管理ができていないんじゃないかという感じがしたわけです。この方みたいに遠くに依頼してもいいとは思いますが、それだけリスクはあります。設計はできても、施工管理という部分は、かなり手間がかかるからです。
絵を描くのは自分だけでできても、それを具体化するにはいろいろな人が関わる必要があります。気候だとか、いろいろな気象条件を踏まえて施工しなくちゃいけないので、遠くの住宅会社さんに頼むなら、そこまでを含めてちゃんとできるかどうかを確認しなければなりません。住んだ後に何か問題が起こったら、困りますよね。いずれにしてもその設計士さんは、そういうのを含めてやられたということなんでしょうね。
私には、カメラで管理するというのがよくわかりません。遠方管理するんだったら、自由設計はまずいんじゃないかという気もします。規格化した家とか、同じものを作り続けるんだったら遠方管理でもいいと思いますが、自由設計でいろいろな材料を使うのにカメラで管理するというのは、なかなか厳しいんじゃないかという感じがします。職人さんを疑っているわけではありません。また、人を信用することは絶対に必要です。ただその裏側に、ちゃんとしたチェックというものがなければまずいという風に思います。