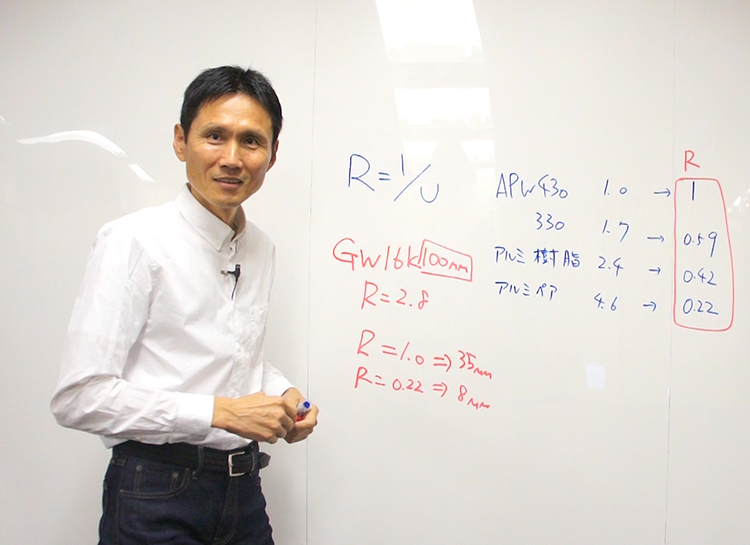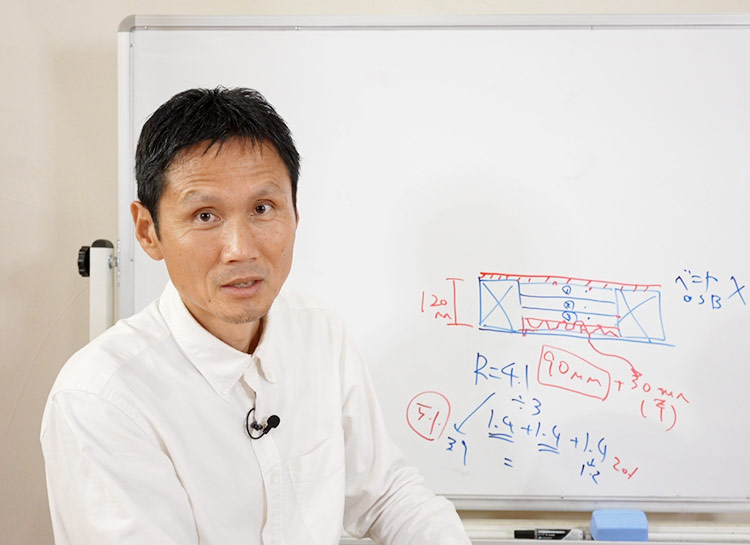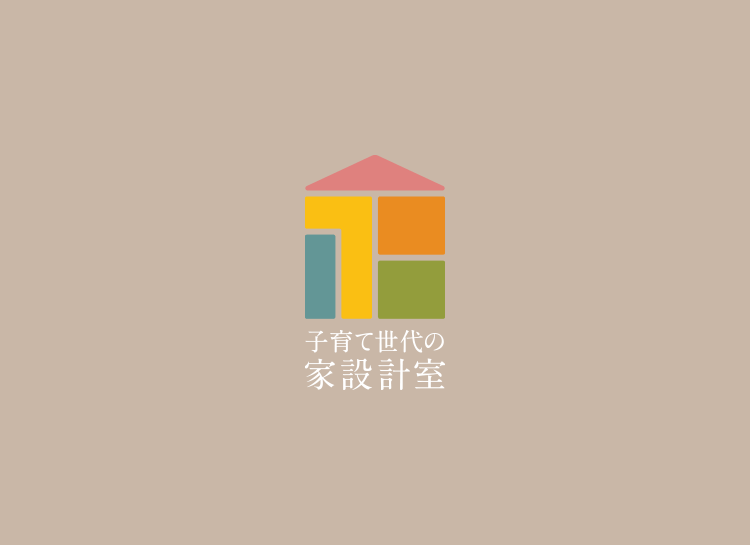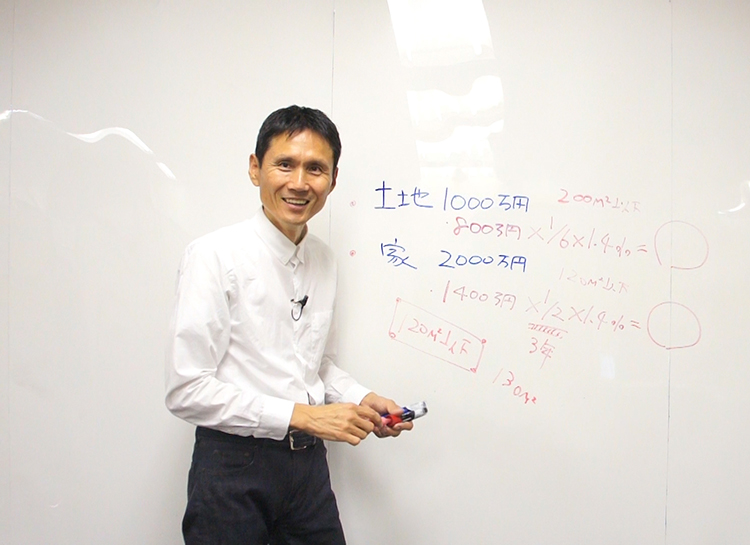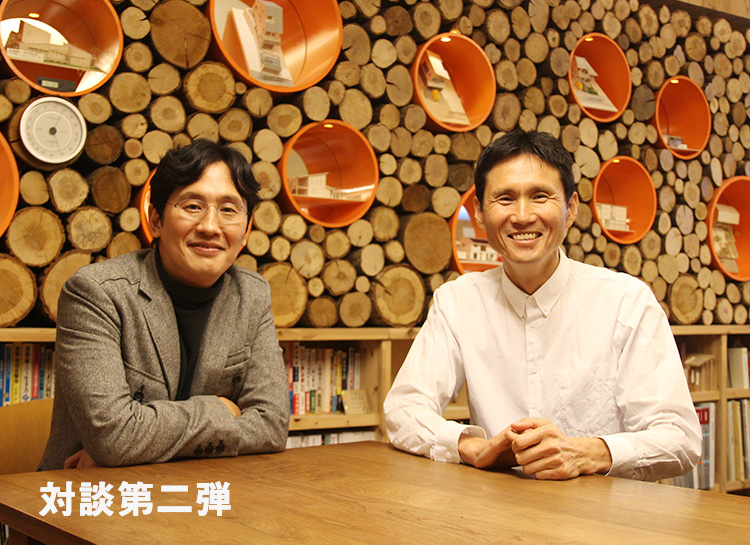今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。
1つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。
◼︎①30坪4000万円もするのに・・・②ハウスメーカーが無垢床を使いたくない理由③30年耐久の本当の意味④15年で350万円の延長保証費用
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/30tsubo_4000_manyen/
「Sで家を建て4年が経ちました。人生2度目の家づくりでした。当時はいろいろな住宅関連のYouTubeを見ていましたが、現在は小暮さんと、時々森下さんのを見ています。家づくりのための情報というよりは、生き方・考え方の参考にします。
30年、60年保証について、メーカーより貰った保証書に基づいてコメントします。メーカー点検は無償で、1年、2年、5年に実施し、その後は30年まで5年ごと、それとは別に、お金がかかるメンテナンスは、10年ごとの防蟻処理と15年目のバルコニーのみです。
そして30年目に大規模なメンテナンス工事があります。30年目の工事を実施するかどうかは施主次第ですが、実施すればさらに30年の保証となり、計60年保証となります。30年目当時の内訳と見積金額も提示されています。
金額から推測ですが、屋根と壁は貼り直しと思われます。前の家では10年ごとぐらいにペンキを塗っていましたが、そういったことは不要です。
この方は2度目の家づくりということなので、最初は地元工務店さんかどこかで、サイディングの一般的な家を作って住まわれていて、塗り直しを何回かした経験がある方なんでしょうね。それで困っちゃったから、今回はハウスメーカーさんに頼んだのかなと思います。
30年目には屋根も外壁も全部やると説明されたとのことですが、おそらくそれでは済まない状態になっていると思います。キッチンからお風呂まで、全部取り替えなければいけないわけではありませんが、ほぼフルリノベーションが必要な感じがします。
おそらくこのSさんの家は、そんなに高性能系ではないと思います。ハウスメーカーさんの家というのは、断熱や窓の性能の不足が顕著に出てくるので、そこまで手をつけないと、住み心地はよくならないと思います。結露問題や、壁の中のカビ問題も発生するので、この辺りのことを考えると、30年後に壁と屋根を張り替えて、さらに30年住むのは厳しいんじゃないかなというのが率直な感想です。
この方の家が悪いというわけではありませんが、ハウスメーカーさんの家はオリジナル商品を使ったりと特殊なことをやっているので、どうしてもメンテするのにお金がかかります。相手の言いなりになっちゃうこともあるので、そういうところを考えながら家づくりをされた方がいいんじゃないかという感じがします。
いずれにしても家というものには、お金がどうしてもかかります。ノーメンテでいい家はありません。なので、なるべくお金がかかりづらくしたり、かかるとしても誰でもできるようにしておくというのが1つのポイントかなと思います。また、そのためにはどうするのかというところまで考えないと、嫌になってしまうと思います。
まずは、機械をたくさん使わないことです。特に、オリジナル空調システムとか、オリジナル換気システムといった、あまり一般的ではない機械は使わないことが原則です。さらに、塗らなければ持たないような素材は使わないことも重要です。一番わかりやすいのはサイディングです。最近はいいものもあるので、一言でサイディングとは言えませんが、安いサイディングはあとでお金がかかります。塗装に関してだけでなく、反りが発生しやすくなるためです。屋根についてもまた然りだと思います。
また、無垢でなければ絶対にいけないというわけではありません。ちゃんと断熱と気密を取って、床下をベタ基礎にして、湿気が上がらないようにすればフローリングでも持ちます。30〜40年と使っていけば、傷ができたり、日焼けしてきたりするのは当然ですが、フローリングはさらに色が飛んできたり、中の肉が出てきたりするので、無垢とは汚さが全く違います。それを補修する方法もありますが、無垢にしておけば内輪で済むかもしれません。
キッチン、ユニットバス、洗面台などの水回り製品は、メーカーさんによって耐久性が違います。40年ぐらい経った家を建て替えすることがあるんですが、タカラさんのホーローを使っているお家は、多少サビは発生していても腐ってはいないし、ガッチリしています。その逆で、木を圧縮して作ったようなメーカーさんのキッチンは、表面の見てくれはいいですが、実際は厳しいところがあります。そもそも圧縮した木はビスを打っても弱いので、何年も持たせるのはなかなか難しいです。
家の気密や断熱をちゃんとして、床下から湿気が上がってこないようにしていけたらいいですが、床下を換気しても、その湿気が家の中に入ってくる状態になってしまいます。キッチンの下は日陰になっているので、そういうところからどうしてもやられてしまうケースは多いです。キッチンだけの問題ではありませんが、この辺りについても気をつけた方がいいのかなと思います。
その他にも細かいことはありますが、それは過去の動画で解説していますので、ご興味があったら見ていただきたいです。否定するような感じになってしまったかもしれませんが、そういう意図はありませんので、ご了承ください。
2つ目のコメントです。先ほどと同じ動画に対していただきました。
「質問ですが、三種換気にして排気口を床下にしたら、床下に換気口を付けたら二種換気になります。この方が壁に穴を開けずに済み断熱性が上がりませんか?」
二種換気と三種換気は、全く違うものです。まず一種換気というのは、機械で入れて機械で出すみたいなイメージです。強制的に吸い込んで、強制的に出すという、高性能住宅ではよくやる方法です。吸気して排気するだけじゃなくて、熱交換もするわけです。今の時期だったら、中は冷房していて冷たい空気がありますよね。対して、外は暑いじゃないですか。この暖かい空気と冷たい空気を混ぜて、なるべく暖かい空気を中の温度に近づけてから入れることで、いきなりドバーンと暖かい空気が入るわけではなくなるので、室内の温度が上がりづらくなるし、エアコンにも負荷がかかりにくくなります。
三種換気というのは、機械で出して自然に入れるというイメージです。当社がメインで使っている方法でもあります。入れるところに蓋をつけておいて、蓋の開け具合と換気扇の強さによって、入ってくる空気と出てくる空気をコントロールします。二種換気というのは、これの逆です。強制的に吸い込ませて、自然に出すという感じです。
それぞれ、メリットもあればデメリットもあります。一種換気は、機械で強制的にやって、さらに熱交換もするので、理想的な方法ではありますが、どうしてもコストがかかります。それなりの機械を使って換気するわけですから、壊れたらまた更新していかなければ、機能としては維持できません。
一種換気をつけて熱交換をして、暖かい空気をドバーッと入れないようにして、湿気を取れば、家の中がものすごく快適になりそうですよね。ただ、それも正直ケースバイケースです。一種換気だけで家の中の湿気が飛ぶわけではないからです。あくまでも換気だけしかしないので、そこだけで家の中がすごく快適になるということは、私の経験上はありません。
どんな高性能の家でも、エアコンでコントロールしなければ住めないし、冬であれば暖房機がなければ住めません。一種換気はあくまでも補助として機能はしますが、メインではありません。また私は、三種換気でも同じような効果が出せると思っています。なので、要望がなければつけていません。
二種換気を住宅でやるというケースはなかなかないですが、パナソニックホームズさんだけはやっていたはずです。おそらく、デメリットの方が大きいからだと思います。熱交換と湿度交換をするのであれば、それなりのメリットはあると思いますが、単純に空気を押し込むだけで、熱交換も湿度交換もしないのであれば、別に三種でも同じじゃないかと思うわけです。
医療の現場だったら、手術室みたいなところでは強制的に換気をしなくちゃいけないので、二種換気でグングン押していくという方法もたしかにあります。また、手術室は家みたいに広い空間ではなく、あくまでも6〜8畳間なので、強制的に押し込んでも問題はないと思います。あえて家で二種換気にするメリットは、そんなにないんじゃないかと思うし、それだったら三種の方が簡単にコントロールしやすいんじゃないかと思います。
話を戻すと、この方は絵のようにすれば二種換気になると言っているのかなと思います。たしかにそうかもしれませんが、一般的に床断熱の場合、床で断熱と気密を取るわけなので、そうなると空気は中に入っていきません。そもそも換気にならないわけです。ただ、こういう換気方法を取っている会社も実はあります。床下に換気口か何かをつけて、夏に開いて冬に閉じてという風にやっているわけです。それについては以前にメルマガやYouTubeで解説をしましたが、これだけ暑くなってきて湿気が溢れてくると、結露して危険かなと個人的には思います。
軽井沢とか、私が夏にキャンプに行った山奥とか、標高1400mぐらいのところだったらいいのかなと思いますが、今は北海道でも35℃になるので、標高が1400m以上限定の工法ということだったらいいと思います。標高500mのところでは、絶対に無理だと思います。最後に某工法をディスってしまいましたが、参考になれば幸いです。