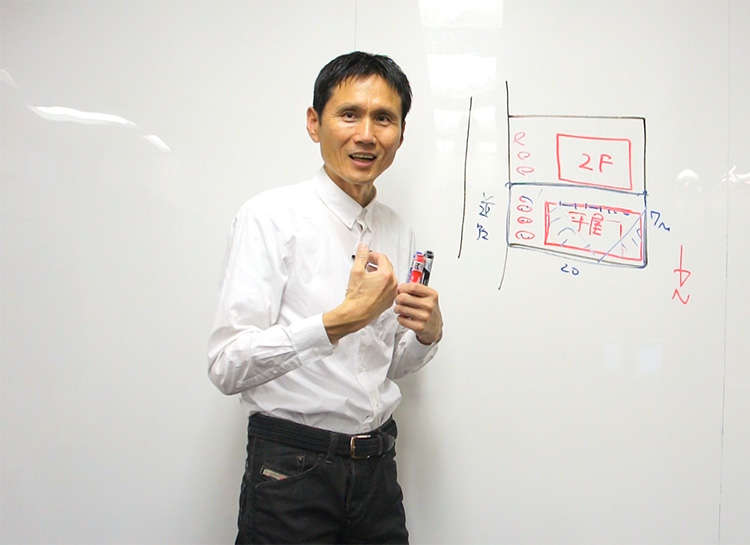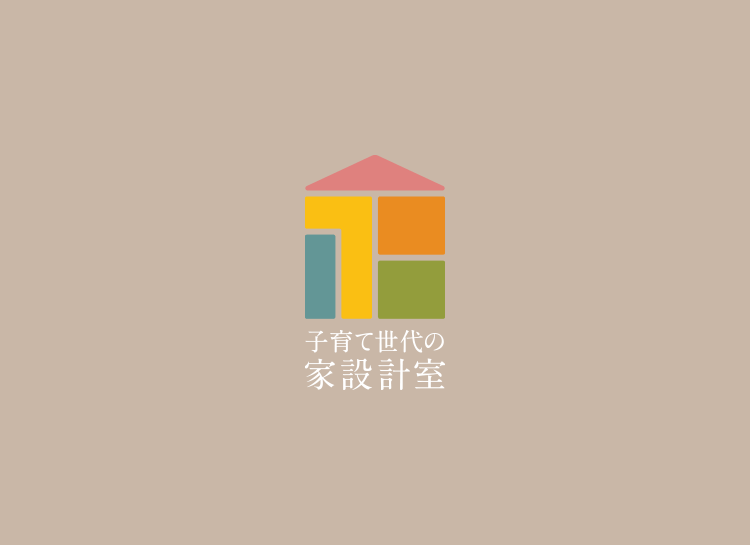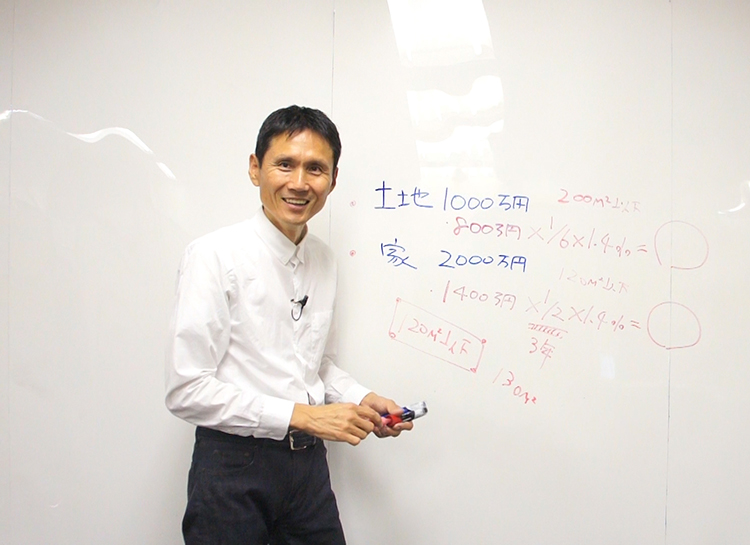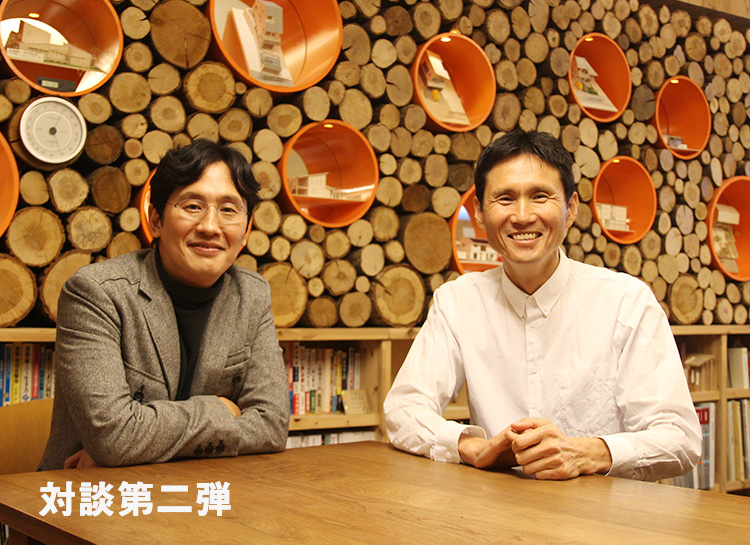今回は、メルマガにいただいたコメントをみなさんにご紹介します。
まず最初はnobandさんからのコメントです。
「お世話になります。最近は電力会社のホームページから、毎日の消費電力の情報やら昨年同時期の消費電力やらが調べられるので色々試してます。個人的に今試していることとしては、“エアコンは止めない方がいいという定説に抗う”です。常時つけておいた方が諸々、カビ対策になったりするような気もしますが。」
そもそもカビってそんなに生えるものなのかな?と思います。ちゃんと気密・断熱性能を上げて、冬は日射取得で室温を上げている家であれば、カビが生えるような気はしません。パッシブ設計で日射取得ができる家を作れば、冬の寒い時期でも室温は18℃ぐらいにはなります。ZEH住宅だと10℃ぐらいにしかならなかったりしますが、断熱性能という部分だけでなく、間取りや窓のつけ方という部分もあると思うので、一概にZEHだからという風には言えません。UA値だけでなく、窓のつけ方や建物の向き、日の入り方を考えなければ、室温というのはなかなか上がりません。また、ひいてはそれがカビ対策になるんじゃないかという感じがします。
「計算上、夏場よりも冬場の方が電力を使うとシミュレーションで見た気がしますが、遮熱型ではないハニカムシェードを下げて明け方と夕方前に少しエアコンで暖めれば十分っぽく、また夏場と比べてそこまで電気は食わない気配です。エアコンで暖めなくても朝方20℃以上にはなっていたのですが、猫が寒そうなのでとりあえずエアコンはつけてます。」
前の動画で、昨年お引き渡しをした家のお客さんと、その前の年にお引き渡しをした家のお客さんからいただいた電気情報を紹介しました。日射取得ができるのとできないのとでは、全く電気代の食い方が違います。ただ、冬場は日射取得ができるかできないかによってエアコンの使い方が違ってくるため、電気代の食い方が変わるということはありますが、夏場に関しては、屋根裏エアコンを24時間ずっと回しっぱなしなのに、そんなに電気代を食っていなかったりします。
遮熱型のハニカムシェードは、はっきり言って暗闇にしちゃう感じのものです。それをするとほぼ熱をカットしちゃうので、冬場で遮熱型のアウターシェードを使っている部屋だと、日射取得ができなくなって、部屋の中が寒くなってしまいます。夏場は日が当たらなくなり、湿気が溜まりやすいということもあります。うちのお客様でもつけられる方はいますが、西・東・北面はいいとしても、南面に使うのはあんまり勧めていません。ただ、ご商売にもよります。夜勤があったりするお医者さんや警察官の方は、日中にぐっすりと寝たいからという理由でつけることもあるので、ケースバイケースです。単純に、寝室だから遮熱型の方がいいのかなと思って南側につけちゃうと、かえってマイナスになることもあるので、この辺りは気をつけた方がいいのかなと思います。
「コの字にしてしまった罪悪感と防音性の期待から36kGWを無駄に天井に300mm入れたことが効いている気がします。誰も36kGWなんか入れづらいし、300も入れない気はします。36kGWは元々、セルロースファイバーに次ぐ防音性があると期待して導入しましたが、防音性能はソコソコくらいですね。うちは湿式外張の付加断熱なので、1枚通気層を設けて音の振動を絶縁してから密度のある外壁を入れたらもっと防音できただろうなと思います。防音についてはレンガがいいでしょうね。レンガの家も候補の1つで最後まで迷いました。」
36Kのグラスウールは当社も使っていますが、一番高性能なグラスウールなので、これを天井に300mm入れたというのはかなりいい仕様ですよね。去年、防音室や音楽室のある家を作りましたが、防音というのは難しいです。例えばオーディオルームで音を聞くんだったら、カラオケルームと同じように遮音した方が、そんなに大きな音を出さなくても綺麗に聞こえます。ただ、楽器を吹くのに遮音しちゃうと、音がどんどん響いて聞こえちゃうので、そんなに一生懸命吹かなくても音が出ているように錯覚してしまうそうです。なので音楽室の場合は吸音にして、「もっと吹け!」と肺活量訓練をした方がいいらしいです。
レンガというのはものすごく密度が高いものだから、遮音性が上がるのかなと思うけど、コストがものすごくかかるので、その辺りはどうだろうという感じはします。でも自分で作った家を客観的に眺めてみると、いい考察ができるかもしれません。
私は自宅を2回作っています。最初は純和風の家を作ったんですが、断熱・気密性能が全くないので、いい家でも全く住み心地はよくありませんでした。2回目は本当に普通の家を作りました。自分と女房と子どもの5人家族なので、いろいろ考えて6人用ぐらいの大きな家を作ったんですが、予算が合わずローコスト系になりました。一応その当時でも、今で言う断熱等級4にしたんですが、さすがに子どもがみんないなくなって夫婦2人で住むとなると寒いです。どういう前提条件で住む予定なのかとか、そういうところまで考えていかないと、なかなか難しいですよね。
2年前に埼玉県の行田市というところで、家づくりをさせていただいた若いお客さんは、3歳の長男と1歳の次男という、2人のお子さんがいました。家族4人で住まわれる平屋がいいとのことで、お子さんの部屋2つとご夫婦の寝室に加え、ちょうどコロナの影響でご主人が在宅勤務だったこともあり、2畳ぐらいの小さな書斎を作りました。あとはリビングという感じで、全体の坪数的には35坪ぐらいだったと思います。
家の大きさは小さくも大きくもないですが、その後めでたく3人目のお子さんができたので、部屋はどうするんだろう?と思いました。女の子はどうしても、男と一緒の部屋というわけにはいきませんよね。男の子の部屋は5畳ずつ、夫婦の寝室は8畳ぐらいあった気がするので、女の子に5畳の部屋をあげて、その隣は夫婦の寝室として5畳使って、男の子たちは8畳を使うというパターンもあるし、3部屋ずつ分けてあげて、ご夫婦はリビングを使うというパターンも考えられます。いずれにしても、日本の人口を増やしてくれるのはありがたいことです。
次は、以下のコメントについてです。
「いつも参考にさせていただいています。床下エアコンについての質問ですが、ガラリから基礎の匂いがしたことはありますか?床下エアコンを使用した物件の見学会に行ったんですが、家のどこにいてもずっと基礎の匂いがして不快でした。基礎断熱で匂いが上がっていくことはありますか?基礎断熱をやめて床下断熱に変更しようか、検討中です。また、もし床下浸水した場合に、細かな砂を撤去せずに床下エアコンを使用したら、菌や臭いが一緒に上がってこないか心配です。」
私は鼻は悪くない方だと思いますが、コンクリート独特の臭いというのは工事中に飛ぶため、その臭いがずっとツンとくるということは考えられません。当社でもお引き渡しの時に床下を覗きますが、匂いがずっと部屋の中に駆け巡っているということはありません。たしかに基礎断熱にして蓋をしちゃったから、その会社の施工方法だと匂いがしやすいということであれば、床断熱にして流しちゃった方がいいですよね。ただ、基礎断熱の問題というわけではなく、その会社の施工的な問題ということであれば、話は違ってきます。
床下浸水した場合は、基礎断熱よりも床断熱の方が怖いです。床下断熱の場合は通気口を取るので、床下浸水したらその分被害が出て危険です。そうは言っても、基礎断熱にして水没した場合、床下エアコンはできなくなります。そういう場合、床も壁も剥がして、断熱材を取って、菌を消毒してから戻す必要があります。ある程度の浸水であれば、施工の仕方にもよりますが、床下断熱よりも基礎断熱の方が強いです。そういう感じだと思いますが、臭いについてはよくわかりません。
次は、以下のコメントについてです。
「いつも楽しく読ませていただいています。素人なので、空調計画はどのようにされているのか教えてください。」
エアコンの選定は、簡単と言えば簡単です。そもそも毎度決めるものではありません。例えば◯坪の家で、窓がこういう風についていて、UA値がいくらというのがあるじゃないですか。そういう中で、エアコンはこの畳数がないとなかなか難しいということがあるわけです。ただ、「うちはこんな小さいエアコンしか使っていない。」と頑張る人もいれば、「そこで頑張っても仕方がないんじゃないか。」と考える人もいます。私はどっちかというと、ギリギリというのは正直良よくないと思うし、そんなに電気代も違わないんじゃないかという感じがします。
10畳のエアコンと14畳のエアコンとでは、金額がすごく変わるわけでもないし、施工方法が変わるわけでもないし、電気代がとんでもなく変わるわけでもないので、家の性能も加味した上で、ある程度の余裕があった方がいいのかなという感じはします。
あとは置く場所ですが、ホームズ君か何かで、このUA値でエアコン1台だとこうなるという風にシミュレーションをしても、その通りにはなりません。秘訣はあるみたいですが、なかなか正しい数値は出ないので、なかなか難しいと思います。何にもない真四角の空間の中に、これだけの熱の出入りがあるから、こういう熱を足せばプラスマイナスいくらと計算はできますが、結局、間取りや壁の位置によって空気の流れは変わってしまいます。さすがに空気の流れまでは、綿密にシミュレーションすることはできません。「それじゃあどうするの?」というと、まずは経験ということになります。
あとは、イマジネーションもあります。空気の流れを綿密にシミュレーションするのは解析ソフトでできますが、そこまでやっても仕方がないし、家全体の温度を平均化していくとしか言いようがありません。最終的には、そこに人が住んだ時に不快じゃない状態を実現するしかないと思います。この部屋は◯℃、この部屋は◯℃という風にするのは無理があります。ただ、温度差が5℃も10℃も出ちゃったらおかしいから、2℃ぐらいに抑えましょうとか、日射取得で南側に当たっていたら北側との温度差が出てしまうので、遮蔽をしてもらって塞ぎましょうというように、コントロールしていくしかありません。
そこまで求められても困ってしまうし、そこまでやらなくても別に不快ではないと思います。言ったら申し訳ないと黙っている方もいるのかもしれませんが、今のところ、不快で困ったと言われたケースはありません。消費者の方の素朴な質問に対して明快な答えではなく恐縮ですが、そんな感じです。