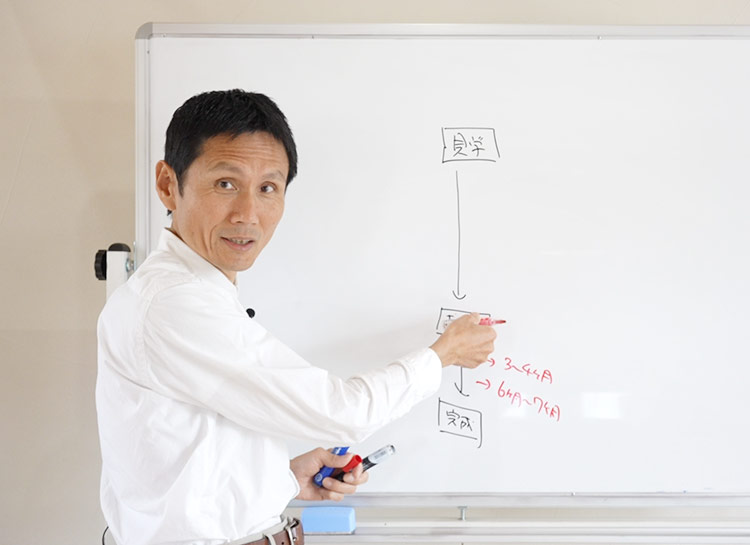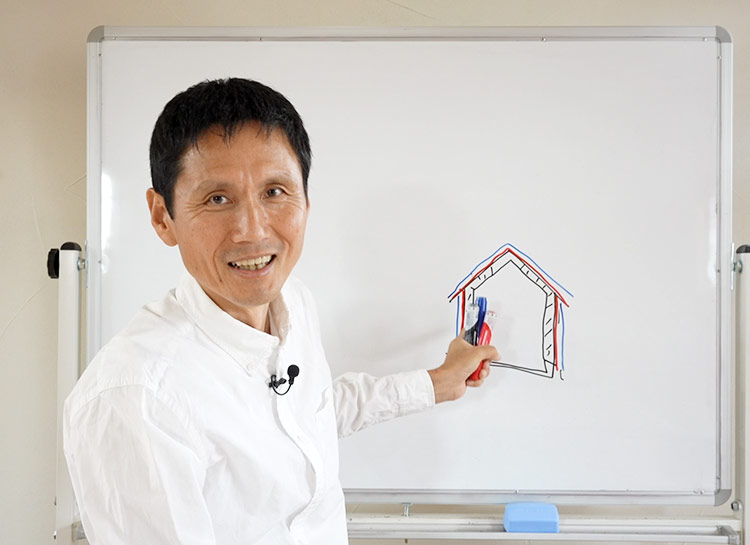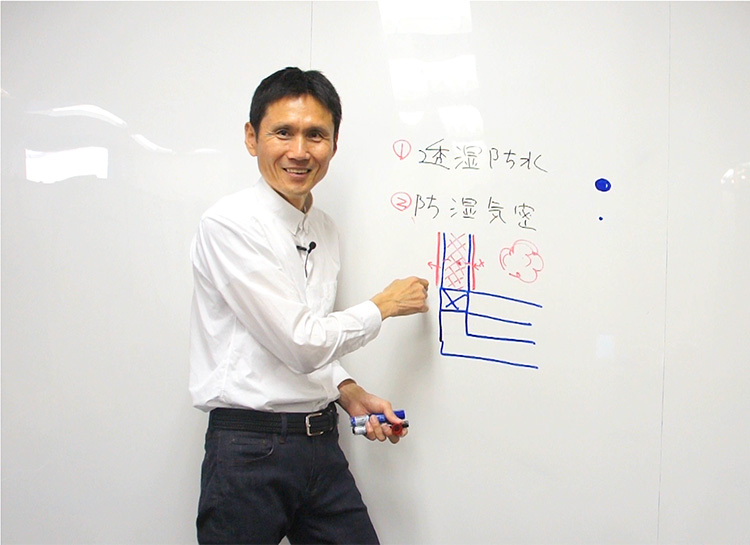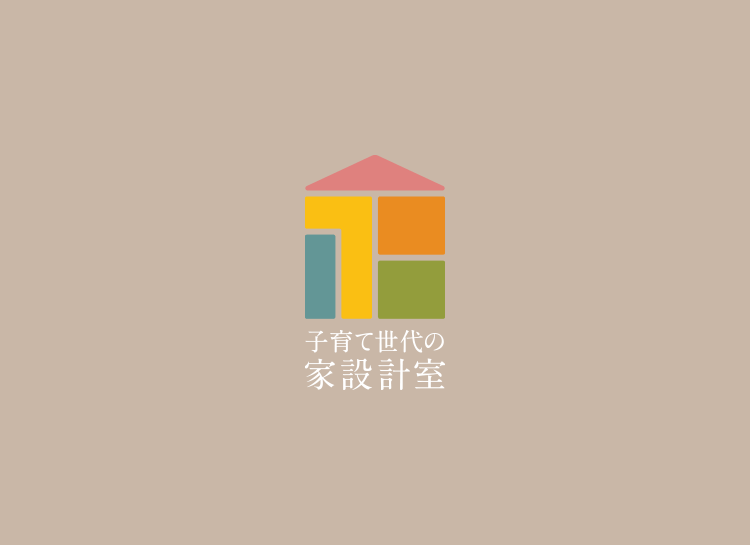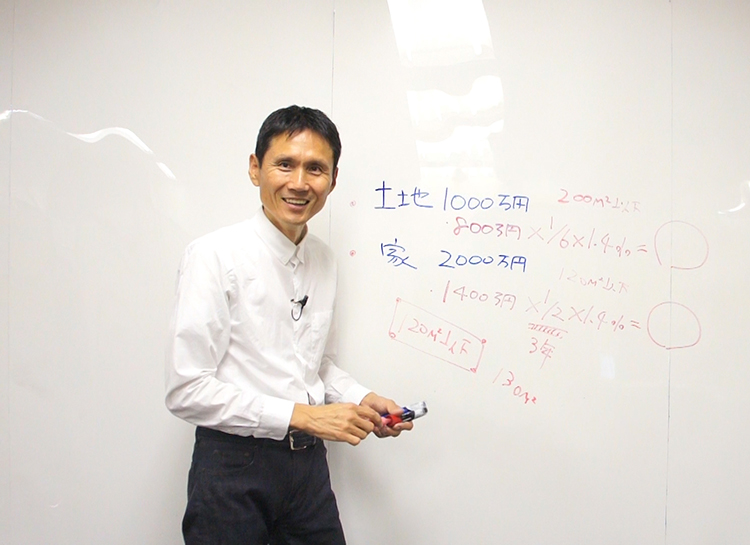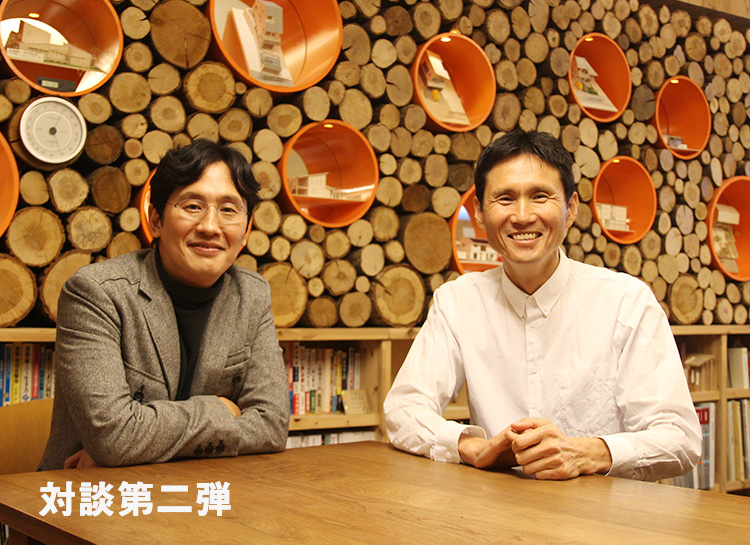今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。
まず最初のコメントです。以下の動画に対していただきました。
◼︎Vol.7 外断熱か、内断熱(充填断熱)か
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/matsuo-2-vol7/
「築古RC戸建住宅の断熱改修を考えているのですが、優先順位的に窓サッシ、天井、床という感じかなと思っています。最後に壁ということですが、壁のことで悩んでいます。元々内壁には薄いグラスウールがあります。業者には内断熱を提案されているのですが、こちらの動画ではRCだと外断熱がいいとのことでした。しかし、予算の都合で外断熱を断念する可能性もあります。となると、第2の手段としての内断熱はしても意味がない?内部結露が発生して逆効果ですか?」
いろいろと不安が生じてしまったんでしょうね。別に内断熱が悪いわけではなく、外断熱の方がより効果があるということです。コンクリートというのは断熱がないようなものですが、水密性や熱容量による蓄熱効果という面で、使いようはあります。
たまにお客さんから「土間のある家ってどうなんですか?」と聞かれます。土間があると自転車が置けたり、趣味のことができたり、子どもさんが工作できたり、薪ストーブを置いたりできるので、木の床とはまた違って、やりたいことが広がります。そういう意味で言うと、土間自体は悪いものではありませんが、コンクリートというのはどうしても熱を吸いやすい性質があります。
昔ながらの玄関は北側にあるのですごく寒いです。コンクリートが冷えて、その冷気が上がってくるので、蓄熱暖房機の逆バージョンみたいな感じになってしまいます。なので土間を作るんだったら、南側の日当たりのいい場所にして、冬の日中はそこで蓄熱をさせて、夜に寒くなったら蓄えたコンクリートの熱を戻す感じにした方がいいと思います。夏は逆にすごく暑くなってしまうので、ちゃんと遮蔽をしなければいけません。
ローコスト住宅や、地元の工務店さんの建てる土間のある家をネットで見ると、「これはどうするのかな?」と思うことがあります。どう見ても高気密・高断熱という感じがしないとか、デザインがバリバリ優先されているとか、窓はアルミかアルミ樹脂なんだろうなという感じだからです。
ましてや外壁がコンクリートだったら、思いきり熱の影響を受けるので、夏であればすごく蓄熱をしてしまう可能性があります。冬であれば放射冷却によって、特に北側はすごく冷えてしまいます。そういうことを考えたら、外側で断熱をしてカットした方がいいということになります。内側で断熱をしてもいいですが、冷えて中まで来る物体を内側でガードするよりも、外側で躯体を冷やさないようにした方が効率がいいと思います。
内側でやる場合は、外側でやるよりも断熱材を厚くして、より高断熱にする必要があります。それでも、外に足場を組んで張るよりは、トータルでは安くなったりします。断熱材を厚くする分のコストはかかりますが、足場代や仮設代などのお金はかからないからです。これについては本当にケースバイケースなので、コストなどの条件を考えながら決めればいいんじゃないかと思います。
ちなみに、この方の築古RC戸建住宅の断熱材ですが、床がグラスウール50mm、天井と壁の発泡ウレタンが15mmとのことです。断熱というよりも水分防止みたいな感じがしますが、昔はこんなものだったはずです。熱抵抗値はないことはないですが、コンクリートが暖まる方に負けちゃうかなという感じがします。
「現状、夏は2階が特に暑くて、1階の西日が当たる部屋はサウナみたいです。冬は寒いです。」とのことですが、そうなりますよね。こういう家の場合は外側からやるのがベストだけど、内側でしっかりとやるのもいいのかなと思います。コンクリートの戸建住宅は、火災に強いとか、音がカットできるというメリットもありますが、沖縄では塩害の問題もありますし、快適さやコストを考えたらなかなか難しい感じがします。
また、耐用年数は意外に短いです。鉄筋コンクリートはものすごく硬くてガッチリしているように見えますが、首都高の橋脚を見ればわかるように、50年ぐらいがMAXです。何もせずに50年がMAXというわけではありません。中に入っている鉄筋が錆びてくるし、収縮してひびが入ってくるので、途中途中で補修する必要があります。
私が前職でゼネコンにいた時に、橋脚や学校の補修工事を請け負ったことがありましたが、大変でしたし、なかなかのお金がかかっていました。コンクリートは硬くて強いし、耐火性があっていいですが、長い目で見ると意外に大変なものです。
公共物がなぜコンクリートでできているのかというと、耐用年数もそうですが、一番は避難場所になるからです。火災や災害の時に地域の方が避難するとなっても、コンクリートだったら倒れにくいし、流されにくいですよね。小学校はお子さんが行くところだから、地震で倒れたら困るので、あんまり揺れずに済むコンクリートがいいんでしょう。
ただ、それを個人で作るとなると維持費が大変です。今は木造でも耐震性能が発揮できるようになっているので、考え方も変わってきていますが、お役所の人の考え方もあるので、なかなか難しいところです。
次は、以下の動画に対するコメントです。
◼︎①お客さんのお家の年間電力消費量②遮熱型ハニカムシェードを付けるときの注意点③計画通りにいかなくても良いこともある④床ガラリからコンクリートのニオイが漏れる⑤空調計画はイマジネーションといい加減さ!?
①お客さんのお家の年間電力消費量②遮熱型ハニカムシェードを付けるときの注意点③計画通りにいかなくても良いこともある④床ガラリからコンクリートのニオイが漏れる⑤空調計画はイマジネーションといい加減さ!?
「正直なお人柄で信頼できます。太陽光発電のメーカーが出す予想発電量は少なめに感じますが、いかがお考えですか?」
人間、正直が一番です。なぜ私が正直に話すのかというと、クレームを言われたくないからです。余計なことや心にもないことを言って「何だよ!」と怒られるのは嫌ですし、小心者なので気にしてしまいます。できないものはできない、余計なことは言わない、わからないものはわからないと言った方がお客さんのためになるし、私の身のためにもなります。
逆に言うと、心にもないことを言える人とか、嘘も方便みたいな感じの人は、クレームなんて気にしないんじゃないかと思います。大きな会社を作りたいんだったら、細かいことは気にしないくらいの根性がなければいけません。私はそもそも人を使えるような人間じゃないし、気の合う人とちょこちょこやっていく方が楽しいと思うタイプなので、そういうのは無理ですが、これも個性かなと思います。
太陽光の予想発電量は、絶対に正しいわけではありません。建っている家の条件によっても変わってくるじゃないですか。建物の向きと太陽光をつける角度は当然プログラムできますが、周りのシチュエーションや建っている条件までは、さすがにプログラムできません。
また、予想発電量が少なめに感じるとのことですが、少ない分には文句はないだろうということだと思います。当社は田舎で作っていることもあって、発電量についてはそんなに違いはないですが、売電量については違います。でも今は売電をするよりも、なるべく自己消費した方が得なので、シミュレーション上は2〜3割が自己消費、7〜8割が売電というのが一般的だと思います。
当社のお客さんのお家だと、4割は自己消費、6割は売電という感じです。おひさまエコキュートをつけるとか、夏は日中エアコンを回しているということもあるんでしょうね。なるべくだったら自己消費を4〜5割ぐらいにして、半分ぐらい売るという方がいいんじゃないかと思います。
次も、先ほどと同じ動画に対するコメントです。
「近くの工務店で聞くと“経験と勘”と言われたので、どうなのかな?と疑問に思いました。」
この方からはたしか「どのように空調をやっているんですか?」という質問をいただいた気がします。何かソフトを使っているのか、それとも経験なのかということです。
ソフトはUA値計算に使ったりしますが、床下エアコンや屋根裏エアコンを使っている場合、そのソフトはあまり上手く使えないかなという感じがします。床下エアコンと屋根裏エアコンを稼働させて、計算上はこの家は断熱がこれぐらいで、熱損失がこのくらいで、これだけの熱があるという感じだったらプラスマイナスゼロになりますが、家には壁があったりするわけです。
下田島モデルハウスのように吹きざらしだったり、1階は壁が少なくて、トイレと洗面所とドアがあるぐらいという状態であればソフトと同じ計算ができますが、プライバシーや音の問題もあるので、実際にここに住めるのは、おそらく仲のいい夫婦とか、おひとり様ぐらいになってしまうと思います。
結局は計算といっても、空調計算までは無理です。あくまでも経験と勘で、ソフトは参考に使うぐらいという感じです。経験と勘というのは、日頃測定をしている客観的事実をもとにしたものです。昔の大工さんみたいに「この辺に筋交いを入れておくか!」という感じではありません。客観的な事実のない経験と勘はまずいと思います。
元◯◯というのは好きではありません。元大工社長の工務店というのは、それ自体はよくても、元大工というところだけで信用するのはまずいと思います。その人がどういう経験をしたのか、その会社がどういう家を作っているのかというところをちゃんとチェックしていかなければいけないと感じます。