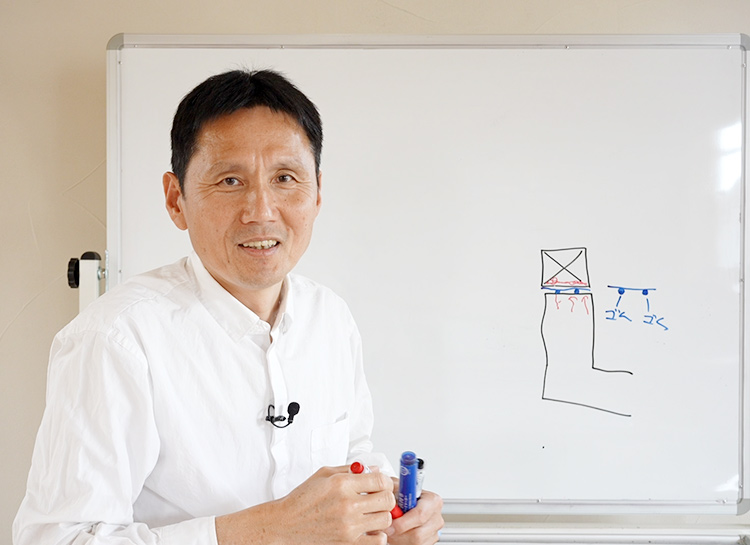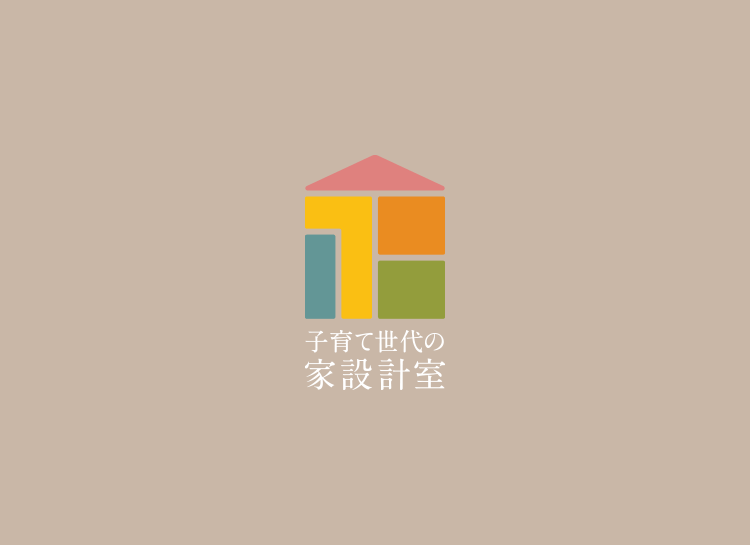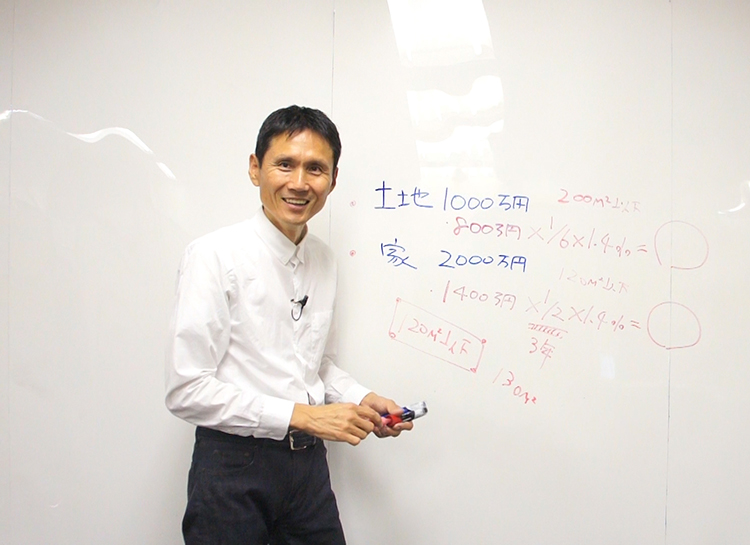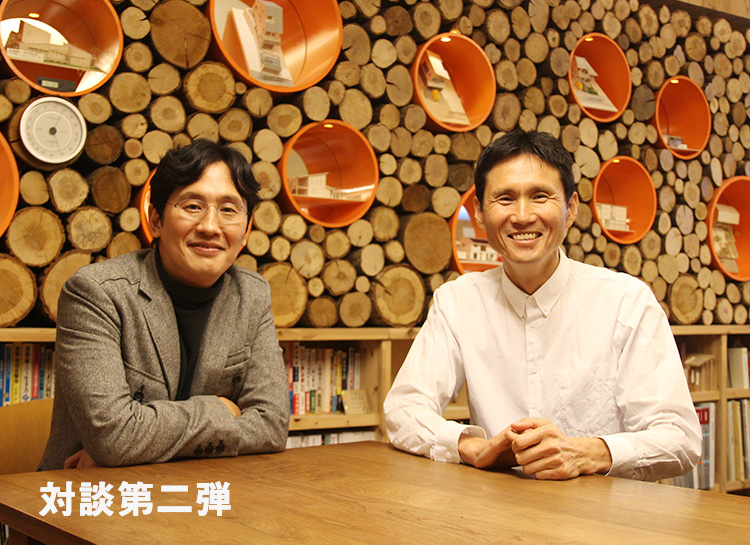今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。
1つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。
▼①他社に決めた理由は何か?②セルロースファイバーの性能は悪いけど安い③ルーフィングと野地板の間で結露はするか?④ガルバ屋根の最大の欠点
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/tasya_kimeta_kiryu/
「天井断熱の家の小屋裏にセルロースファイバーを吹き込み、天井一面に積もらせる断熱の方法はどう思いますか?私は3点気になっています。①小屋裏で電気関係に問題があった時に対処が難しくなるのでは?②いつか屋根の葺き替え時などに屋根断熱に変更するのがほぼ不可能③断熱材に調湿効果があるのは断熱性能には逆効果では?」
まず③についてですが、セルロースファイバーに調湿効果はありません。ここは勘違いされている気がしますが、いいところをついていると思います。もしセルロースファイバーが調湿材なんだとしたら、断熱材にはなりません。水分をグングン吸ってしまったら、断熱性能は低下してしまいます。そう考えると、セルロースファイバーに調湿効果があったらまずいですよね。
①に関しては、以前YouTubeやメルマガでも解説をしたように、ブローイング工法を使います。絵のように、セルロースファイバーやグラスウールを吹き込むとします。その時、配線を埋めてしまうとまずいので、天井を二重に作って、その間に配線を通していきます。セルロースファイバーが載っかっている空間の下にもう1つ空間があって、そこに配線が来ることになるので、何かあったら天井の点検口をパカッと開ければいいわけです。
水道のプラスチックのホースみたいなものを入れて、その中に配線をしていくという手もあります。何かあったらその配線を引っこ抜けばいいので、悪くはないかと思います。生の配線の上にズボッと載っけてしまうのは、よくありません。リフォームの際にはそのまま埋めてしまうこともありますが、配線を持ち上げて上に吊って、その配線の下でブローイングするようにした方がいいとは思います。あとから屋根断熱を足す場合には、細かいことが必要になってくるのが事実です。
②に関してですが、屋根断熱をする場合は、100%外付加断熱になると思います。通気は取らなくちゃいけませんが、天井と屋根でダブル断熱をすることになるので、別に悪いことはありません。もしかしたらこの方は、リフォームを考えられている方なのかもしれませんね。
私のYouTubeやメルマガでは新築の話をしていますが、いつかはリフォームの話をするとか、住んだ後の問題点を解決するといったこともしていきたいと考えています。既に作ったものをどういう風に対処するかということについて解説をしているYouTubeは、なかなかない気がするので、どこかでそういうこともできたら参考になるかなと思います。
2つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。
▼①杉板外壁を洗っても良いのか?②レンジフードに〇〇を貼ると家が汚れる③何故、気密を高めるのか?④改めてパッシブ設計の理屈を解説してみた⑤性能の悪い家ほど自然の摂理を無視している
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/gaiheki_food_yogore/
「真冬なら気密の重要性は納得なのですが、春秋は窓を開けて風を入れたい派の人が多いんじゃないですかね。近所でもかなり見かけます。そうなると、湿度も空気の汚れも設備でコントロールする前提は崩れますよね。未だに三種換気がほとんどなのも、住まい方が設備に追いついていないこともあるのかなと思うのですが。」
家をカプセルのように考えて、全く窓を開けず、一種換気で全て処理するというのも1つの考え方です。また、春や秋のように、暑くも寒くもない時に空気を通して、スーッとする感じを楽しむのもいいかと思います。ただ、これはあくまでも地域によります。都心に近い場所や
狭い場所に住んでいる人は、音の問題もあるので難しいですよね。近くに工場があって粉塵などが飛んでくるような場所に住んでいる人も、なかなか窓を開けられないと思うので、そういう場合は一種換気をやってもいいのかなという感じがします。
この方は一種換気にして、窓を開けずに住んだ方がいいと思っているのかもしれません。たしかに、さっき言ったような条件であればその方がいいかもしれませんが、あくまでも考え方によります。私はそういう家でカプセル化して住むというのも、悪くはないと思います。田舎であれば、風や外の空気を楽しむような住まい方をするのもいいと思います。そういう住まい方をすることによって、家の中がカビちゃうとか、何か被害が起こるということなら問題ですが、そういうわけではありません。そもそも当社では三種換気を前提としていますし、本当にこの辺りは作る場所、考え方、住まい方によるんじゃないかと思います。
網戸もつけず窓も開けず、ずっとハニカムブラインドを閉めて住むのは効率的かもしれませんが、私にはどうしても違和感があります。別に問題がなければ、窓を開けてもいいんじゃないかと思います。ちなみにパッシブ先進国のドイツでは、普通に窓を開けているらしいです。意外に日本の方が、ガチガチに考えてしまっている感じがします。
3つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。
▼①羽子板ボルトに発砲ウレタンを吹く理由は何か?②知識と感情と違和感の違い③サッシ下の胴縁が気になる④過剰な家づくりが多くなっているかも
https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/hagoita_bolt_riyu/
「最後の話は、少し苦笑いしてしまいました。年を重ねるとまた感じ方も価値観も変わりますよね。私も今年から巣箱を家の壁に設置して、雛が産まれるのを見守ることが楽しくなってきたりと、いろいろ変化してきました。シジュウカラを迎える予定でしたが、スズメが入居になり、産卵もしまして、それはそれで嬉しいです。また、部屋から見える庭は少しでもあるといいですね。家庭菜園のトマトやレタスの育ち具合を見るのも楽しいです。ある意味、家というのはその時100点でも、年と共に70点になったりするので、ある程度柔軟性を持たせて変えていける設計も大事なのかもしれませんね。」
西の巨匠は、羽子板ボルトに発泡ウレタンを吹くことについて「あれは意味がないけど、消費者の方はすごいことのように思っている。」と言っていました。だからといって、羽子板ボルトに発泡ウレタンを吹いちゃいけないというわけではありません。実際に現場でも、基礎断熱でできた隙間に、大工さんが発泡ウレタンを吹いてくれることがあります。余った分を捨てるのはもったいないし、捨てるにも中を空にしなくちゃいけないので、ついでにビューッと吹くわけです。
ただ、それを吹くのが正しいことのように言う人もいます。そういうことを言う人に限って、ちゃんと測定をしていないような気がします。吹いた時と吹いていない時の温度の違いや、吹かないと羽子板ボルトが結露するかどうかの確認はしていないのに、吹くべきだと言っている感じがします。実際には吹かなくても結露しないし、温度も変わりませんが、だからといって体感もせずにそういうことを言うのはどうかと思います。
家というのは難しいです。若い時の価値観も大事ですが、そこに特化してしまうと、間違いなく年を取った時に「何だかな。」と思うことになるはずです。
灼熱地獄の家は、意外に多いです。その条件としては、軒がなくて四角い、南側にでかいFIX窓がある、鉄骨造であるといった感じでしょうか。こういう家の2階の夏は、かなり灼熱だと思います。また、そういう家に住んでいる人は、真夏に2階の窓を開けているケースが多いです。排熱しないといられないんでしょうね。
そういう家を作るのは、大体は大手ハウスメーカーさんです。消費者の方はやっぱり、大手というブランドで家を買ってしまうんだと思います。どんな家なのかということよりも、「聞いたことのある会社だから大丈夫だ。」という風に考えるわけです。
また、大手ハウスメーカーさんで家を購入する方は、その家がどういう風に作られているかではなく、建て終わった後のことを重視している傾向にあると思います。会社の名前で大丈夫だと判断するのは決して悪いわけではありませんが、まずはちゃんとしたものを建ててもらうことが前提条件だと思います。そうすれば結果的に、メンテナンスコストもあまりかからずに済みます。
灼熱地獄の家についても西の巨匠に聞きましたが、その内容はここでは話せないので、機会があればメルマガの方に書きたいと思います。「もしこういう家に住んでいるんだったら、こういう風に対応する方法もあります。」という風にアドバイスをしたいと思っていますので、楽しみにしていてください。